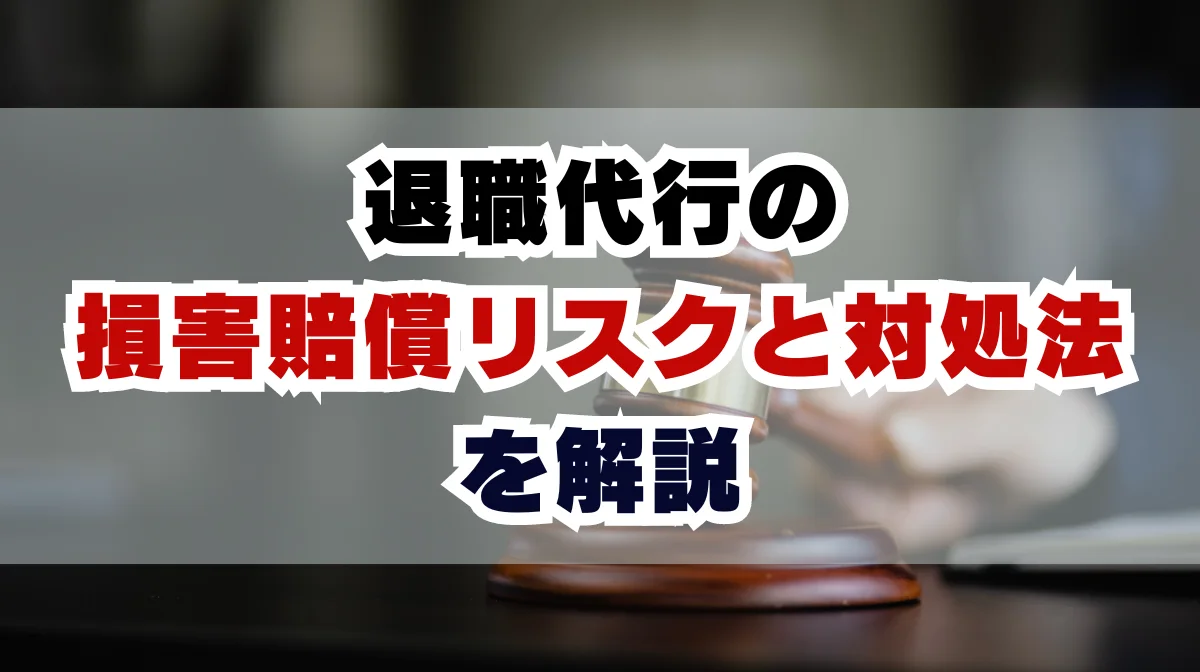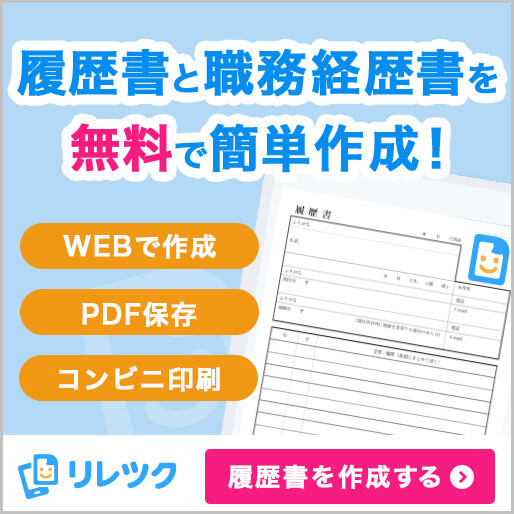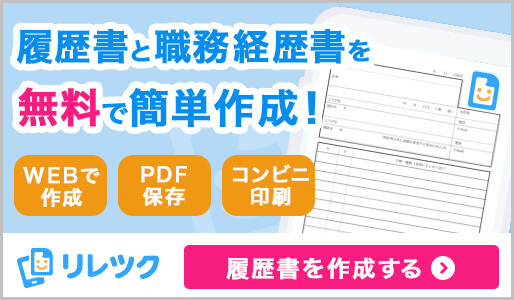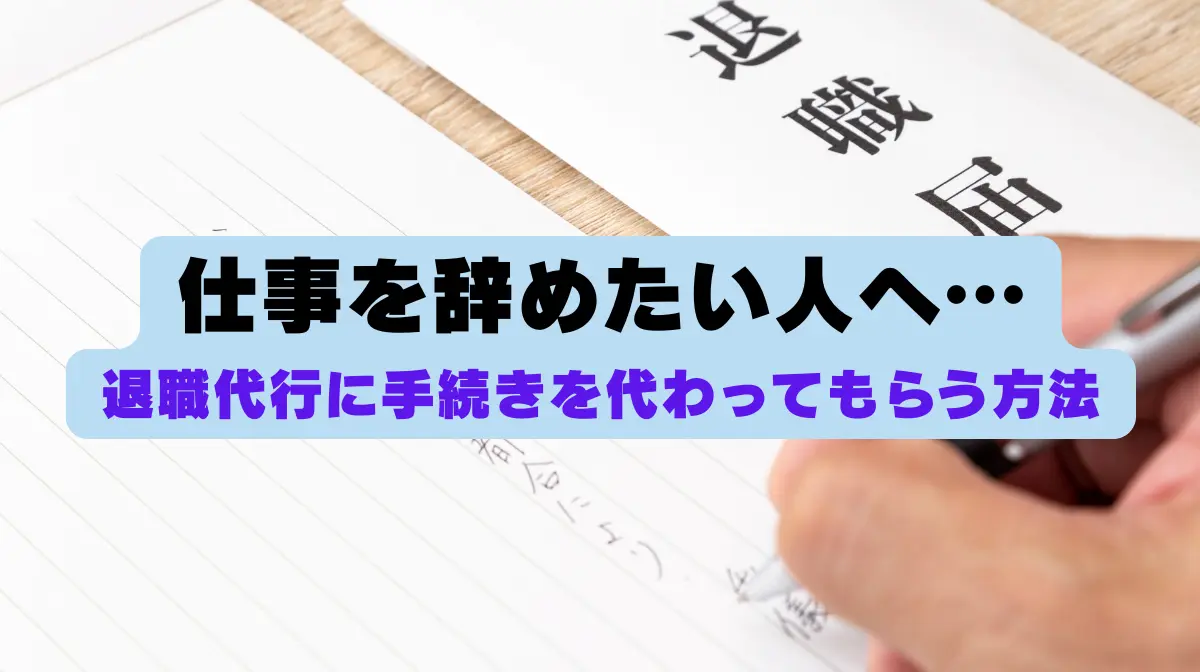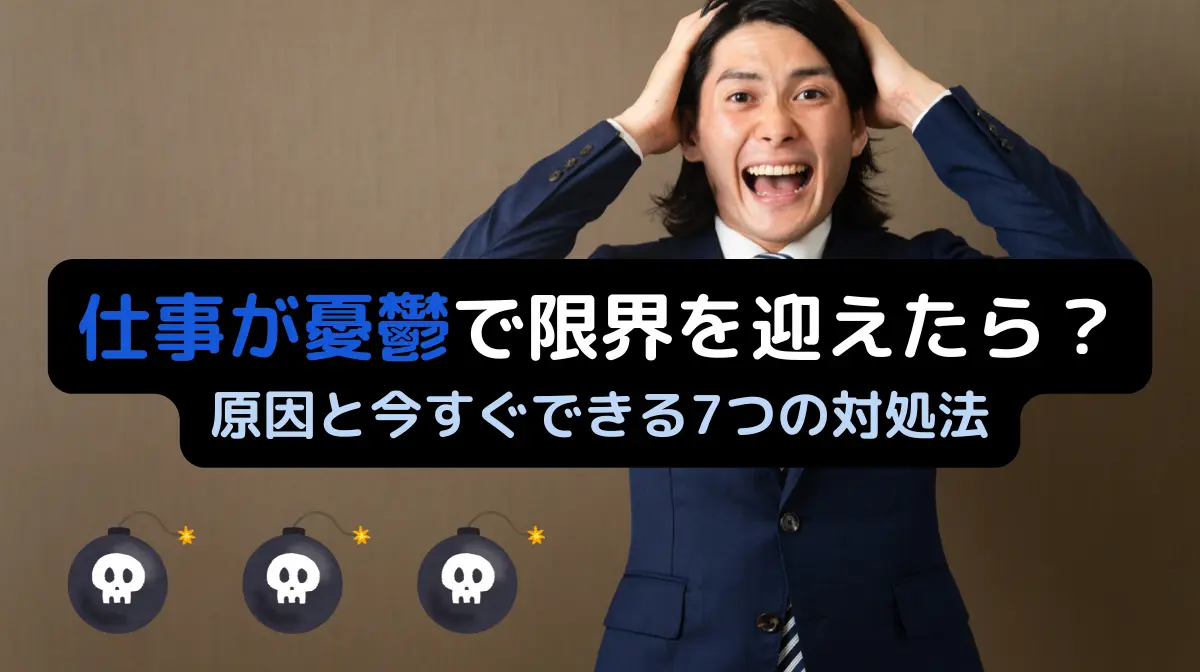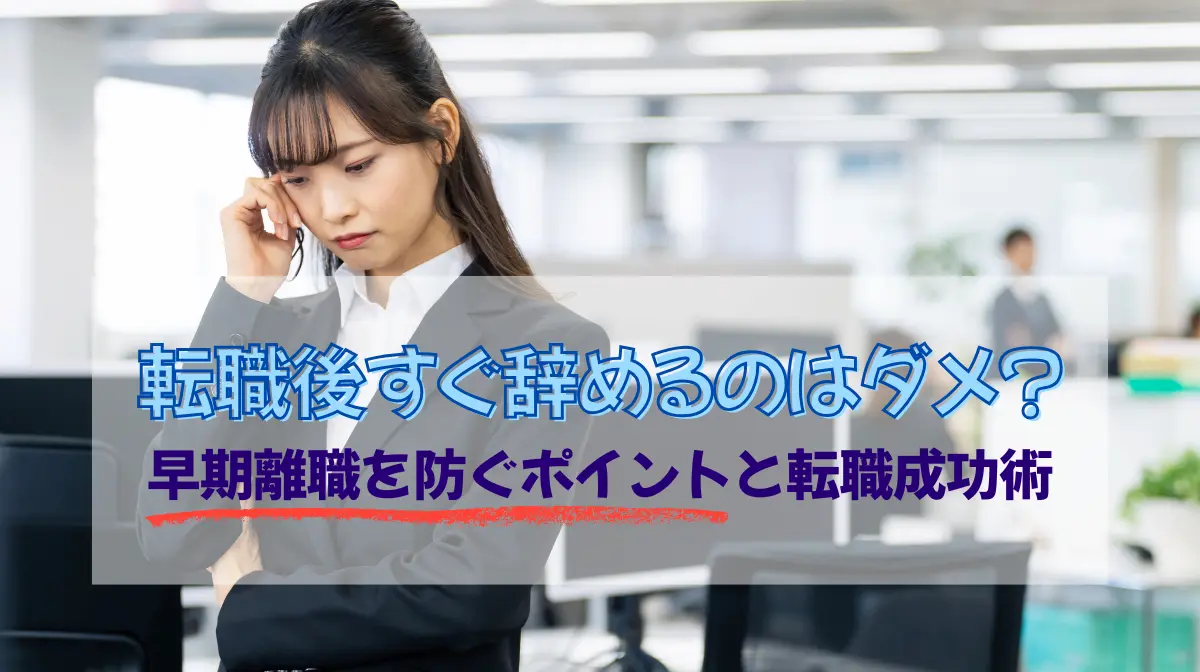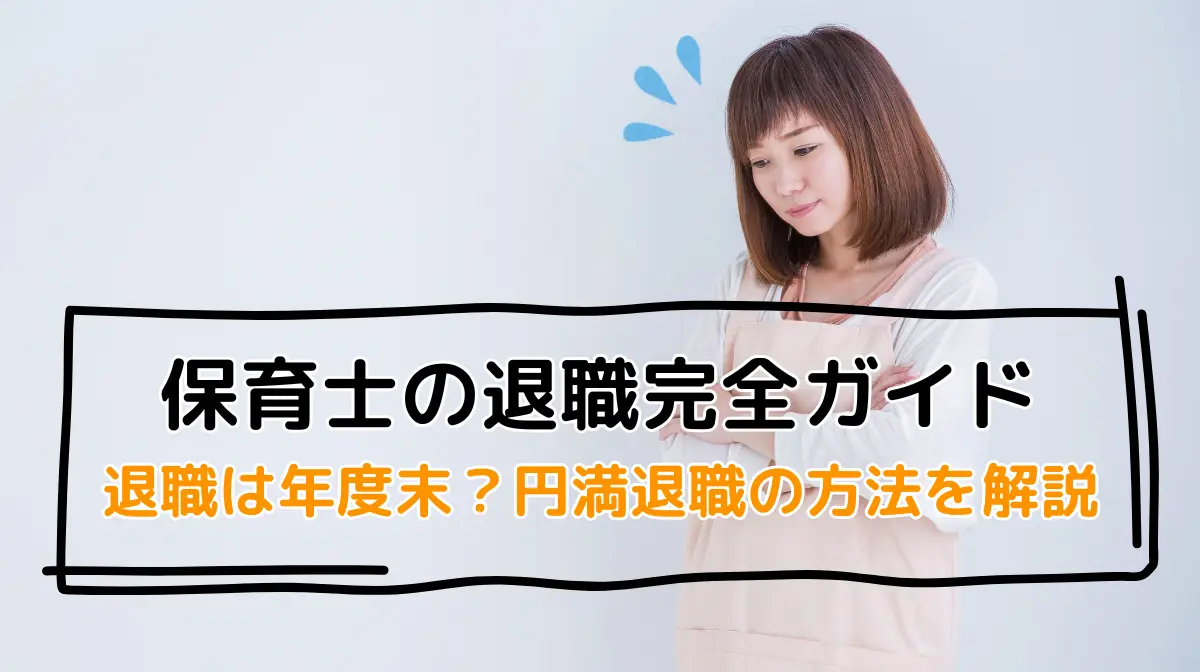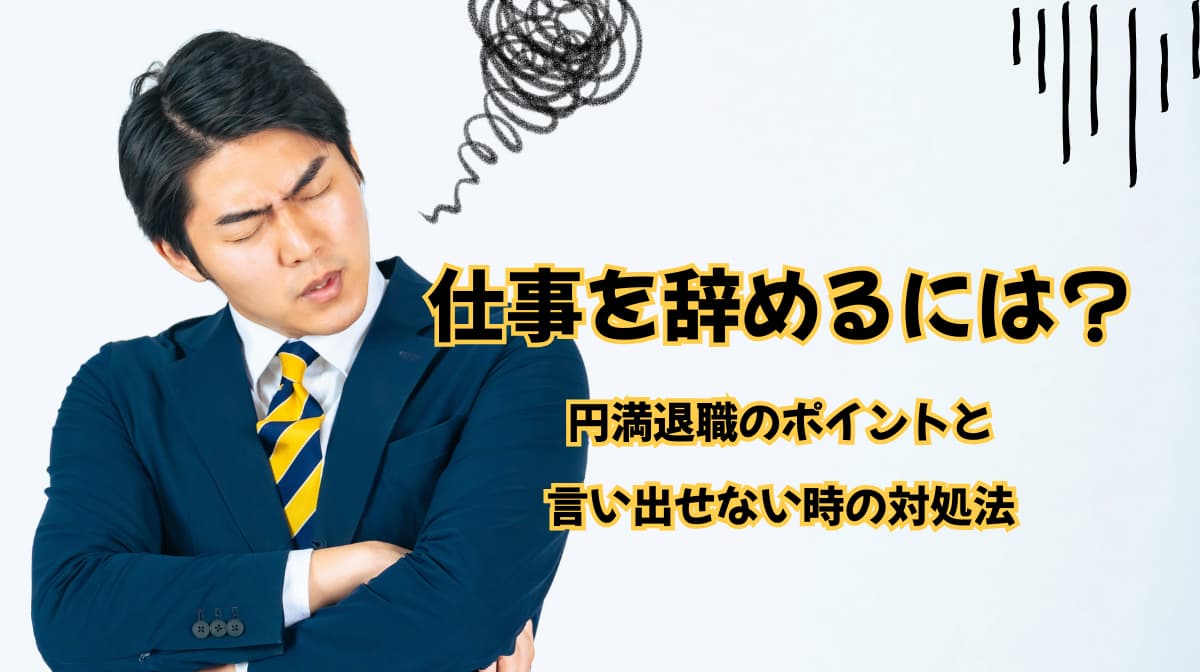「退職代行を使っても、訴えられたり、損害賠償を請求されたりしない?」
「損害賠償を請求されるケースを事前に知っておきたい」
上記のように、退職代行を利用した際の損害賠償請求リスクについて知りたいという方に向けて、本記事は執筆しています。
- 退職に関連する損害賠償が発生するケース
- 退職代行利用時の損害賠償リスク
- 損害賠償リスクを最小限に抑えた退職代行の利用ポイント
1.退職代行と退職時の損害賠償について

退職代行サービスを利用すること自体は合法であり、損害賠償請求を受ける理由にはなりません。しかし、退職に至った経緯によっては損害賠償請求されるおそれがあります。
退職代行サービスとは何か
退職代行サービスとは、利用者の代わりに退職の意思を会社に伝えたり、退職に伴う各種の手続きをサポートしたりするサービスです。
「退職したいと上司に伝えにくい」「退職したいのに会社が辞めさせてくれない」など、さまざまな事情で会社と直接連絡を取るのを避けたい方が利用しています。
退職代行サービスは、民間の事業者のほか、労働組合や弁護士が提供している場合もあります。
退職に関連する損害賠償が発生する一般的な条件
退職代行サービスの利用者の中には、「自分に何らかの負い目があって上司に会いたくないから退職代行を依頼する」という方もいるはずです。
こうした事情を抱えている場合、退職代行サービスを利用している・いないにかかわらず、状況次第で会社から損害賠償を請求される可能性があります。退職に伴って会社に損害賠償請求される主なケースとしては、以下のような例が挙げられます。
- 有期雇用契約を結んでいるのに契約期間中に一方的に退職する
- 無断欠勤を続けてそのまま退職する
- 引継ぎをまったくしないまま退職して会社に損害を与える
- SNSなどで会社の評判を下げるような書き込みをする
- ほかの従業員に引き抜きをかけて退職する
つまり、自分側に責めがあるような事情で会社に具体的な損害を与えて退職した場合は、損害賠償請求されるおそれがあるということです。
一つずつ詳しくみていきましょう。
2.退職代行利用時の損害賠償リスク①:契約違反

まず注意したいのは、会社と有期雇用契約を結んでいるにもかかわらず、退職代行を利用して退職を強行しようとしている場合です。
一般的な正社員の場合、雇用契約は無期契約のため問題がないのですが、特に契約社員や派遣社員の場合には注意が必要です。
期間の定めのある契約の途中で退職する場合
契約社員などで会社と有期雇用契約を結んでいる場合、自分側の一方的な都合で雇用期間中に退職(契約解除)すると、契約違反とみなされ、会社側に損害賠償を請求される可能性があります。この損害賠償責任は民法628条で定められていることです。
なお、正社員のような無期雇用の場合、退職を申し出るタイミングは民法627条1項に基づき「退職の2週間前」までに行えばよいとされています。
参照元:e-Gov法令検索「民法」
契約期間でも退職できる場合
有期雇用契約の期間中でも、やむを得ない場合には損害賠償リスクを負わずに即日退職できます。具体的には、以下のようなケースです。
- 心身の重大な障害や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合
- 法令違反や雇用条件の不履行、ハラスメントなど、会社側に過失がある場合
- 契約から1年を経過した場合(労働基準法137条)
逆に言うと、上記のような事情がなく有期雇用契約を一方的に打ち切ろうとすると、損害賠償リスクが生じます。
参照元:e-Gov法令検索「労働基準法」
3.退職代行利用時の損害賠償リスク②:引継ぎ不足

退職代行を利用すれば、引継ぎの手間もかけず、即座に会社を辞められると期待している方もいるはずです。たしかに法律的には、退職時の引継ぎは義務ではありません。
しかし、引継ぎをせずに退職した結果、会社に重大な損害が発生した場合は、民法415条で定められた債務不履行に該当し、損害賠償請求されるおそれがあります。
参照元:e-Gov法令検索「民法」
引継ぎ不足が損害賠償につながる条件
上記のように、引継ぎの実施は法的に定められた義務ではないので、それをしなかったからといって、ただちに損害賠償請求されるリスクは低いです。ただし、以下のような条件を満たす場合は損害賠償につながるリスクが高まります。
- 取引先の喪失やプロジェクトの大幅な遅延など、実際に損害が発生したこと
- 上記の損害の原因が引継ぎ不足にあることが明らかな場合
「自分が突然退職したら会社は非常に困るだろう」という状況が明らかな場合は、最低限の引継ぎを済ませてから退職したほうが安心です。
最低限必要な引継ぎ内容と方法
損害賠償リスクを避けるための「最低限の引継ぎ」としては、具体的に以下のような内容が挙げられます。
- できるだけ自分の担当業務を完遂させておく
- 引継ぎ書の作成を作成しておく
中途半端な状態で仕事を残しておくと後任者が困りやすいので、少なくとも切りのいいところまでは自分の担当業務を済ませておきましょう。
引継ぎ書には、業務の進捗状況、関係者の連絡先、今後のスケジュールなど、必要な情報を簡潔にまとめておきます。引継ぎをしておくことで、退職後に会社から問い合わせがきて嫌な思いをすることも減らせます。
4.退職代行利用時の損害賠償リスク③:無断欠勤が続いていた

「ある日から無断欠勤を続け、そのまま退職代行サービスを利用して退職する」といった、いわゆるバックレに近い退職は損害賠償リスクを高めます。
というのも、そもそも無断欠勤自体が労働契約における債務不履行に該当し、会社に損害を与えかねない行為だからです。
特に、無断欠勤が2週間を超えて長期にわたる場合は、裁判でも悪質と判断されて損害賠償が認められやすくなります。
長期間の無断欠勤が続くと、退職はできても懲戒解雇という扱いになり、その後の転職が不利になってしまう可能性もあるので注意が必要です。欠勤するなら、退職代行サービスを通して退職の意思や有給休暇の取得申請などを伝達してからにしましょう。
5.退職代行利用時の損害賠償リスク④:会社への名誉毀損
退職代行サービスの利用者の中には、会社や上司との関係が悪化し、強い不満や不信感を抱えている方もいるはずです。
しかし、会社や上司の悪口をSNSや口コミ掲示板などに書き込むと、名誉毀損とみなされて損害賠償リスクが生じるので注意しましょう。匿名アカウントでの投稿でも、情報開示請求によって身元の特定は可能です。
また、多くの会社は、業務上で知りえた情報を口外しないように、入社時に従業員と秘密保持契約を結んでいます。そのため、会社の内部情報などを暴露すると契約違反になり、違約金や損害賠償を請求される可能性があるので控えるべきです。
6.退職代行利用時の損害賠償リスク⑤:大きな損害を出す
自分の過失で会社に大きな損害を出してしまい、そのまま気まずくなって退職代行サービスを利用する方もいるはずです。基本的に、会社の指揮系統の下で行った業務で生じた損害について、従業員が弁償する義務はありません。
しかし、以下のように、会社に対して悪質な行為を働いて損害を出した場合は、損害賠償責任を問われる可能性があります。
- 故意に会社の備品を盗んだり、破損したりした
- 会社のお金を横領した
- 機密情報を故意に外部流出した
上記のような不正行為は、退職代行サービスを利用したからといって帳消しにできるものではありません。会社から貸与されている備品がある場合は必ず返却しましょう。横領や機密情報の流出を疑われる行為もしてはいけません。
7.退職代行利用時の5つの損害賠償リスクまとめ
損害賠償を請求されるおそれがあるケース①~⑤についてまとめました。
これらの項目に注意して、退職手続きを進めていきましょう。とはいえ、退職代行の利用をしたせいで損害賠償に繋がった…とまでは言えません。
退職代行を利用するに至った人のなかには、実際に会社とトラブルになってから退職代行に依頼しているケースも多数存在します。問題は「退職代行を使うかどうか」ではなく、「退職までの経緯」なのです。実際の判例を見ながら、次項で詳しく説明します。
8.実際の判例に見る損害賠償請求事例
退職時に損害賠償を求められた事例を紹介します。実際の流れを見ることで、具体的な司法判断を知ることができます。
ケイズインターナショナル事件(東京地裁平成4年9月30日判決)
【事案の概要】
インテリアデザイン会社であるX社は、取引先A社との3年間1,000万円超のプロジェクトのため、Y氏を専任担当者として雇用しました。しかし、Y氏は入社1週間後から体調不良を理由に欠勤し、そのまま他社でアルバイトを始め、X社を退職してしまいました。
【判決結果】
裁判所は、Y氏の突然の退職により会社に損害が生じたことを認めましたが、請求された200万円から大幅に減額し、70万円の支払いを命じました。
【減額の理由】
- 給与などの経費を差し引けば実損害はそれほど多額ではない
- 会社側が採用時の調査を怠った責任がある
- 無期雇用契約では労働者は2週間前予告で自由に退職できる
この事例は、損害賠償が認められるケースでも、会社が希望するような満額は認められないことを示す重要な判例です。
参考:確かめよう労働条件
プロシード元従業員事件(横浜地判平成29年3月30日)
【事案の概要】
IT企業プロシード社の従業員が過酷な労働のため躁うつ病を発症して退職したところ、会社から「虚偽の病気で退職した」として約1,270万円の損害賠償を請求されました。
【判決結果】
裁判所は会社の請求を全て棄却し、逆に会社の不当訴訟に対して労働者に110万円の支払いを命じました。
【判決のポイント】
- 会社の損害賠償請求には法的根拠がないことを明言
- 不当な訴訟提起自体が不法行為に該当
- 「ブラック企業を返り討ちにした」画期的な判例
弁護士は「退職後の労働者への損害賠償請求は、労働者を萎縮させ、『辞めたいのに辞められない』被害を生む要因となる。この判決は、頻発するほかの不当請求に対しても大きな警告となる」とコメントしています。
参考:【退職】プロシード事件
以上の判例からみるように、会社側が強い立場を利用して理不尽な損害賠償を求めても、本人に相当な落ち度がなければ基本的には認められないことが分かります。
いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるような会社から司法は労働者を保護する立場にたっているので、「会社からの損害賠償請求が怖くて退職できない」と過剰に考える必要はないようです。
9.退職代行を使用すると損害賠償につながるのか

「退職代行サービスを利用すると会社から損害賠償請求をされやすくなるのではないか」と不安を感じている方もいるかもしれません。
しかし、会社から損害賠償請求されるか否かは、退職代行サービスの利用よりも、退職に至った経緯のほうが大きく影響します。
退職代行は損害賠償の直接的な原因にはならない
まず押さえておきたいのは、退職代行サービスの利用自体は、損害賠償請求の根拠にならないということです。そもそも損害賠償とは、加害者の不当な行為によって生じた損失を補填するために請求するものです。
その点、退職は労働者の正当な権利の行使に過ぎません。また、退職の意思を、第三者を通して伝えたからといって、会社に実際的な損失が生じるとは考えにくいです。
そのため、退職代行サービスの利用自体を理由に会社が損害賠償請求するのは現実的ではありません。
10.損害賠償リスクを最小限に抑えた退職代行の利用ポイント

損害賠償リスクを下げるためには、自分側に落ち度を作らないようにすることが大切です。具体的には、以下のようなポイントに注意しましょう。
会社の規定を守って退職する
まずは会社の就業規則や退職に関する規定をなるべく守ることが必要です。退職代行サービスを利用するかしないかは関係なく、会社の規則に違反して損害を与えた場合は、損害賠償請求を受ける可能性が生じます。
逆に言えば、社内の規定に則って手続きをする分には、そもそも退職代行を利用する必要すらなく、スムーズに退職できる可能性が高いです。
なお、法的な優先度は、社内の規定より法律のほうが高いです。たとえば社内の規定に「退職は3か月前までに申告すること」という条文があったとしても、法律上では退職の申告時期は2週間前でよいとされています(無期雇用の場合)。
そのため、会社の規定がどうであれ、2週間以上前に退職の意思を伝えれば損害賠償のリスクは抑えられます。
可能な限り引継ぎを行う
先述のように、引継ぎ不足によって損害賠償リスクが生じる場合もあるので、退職前にはできるだけ丁寧に引継ぎを行いましょう。
特に巨額の資金や大きなプロジェクトに関係するような重要業務を担当している場合は、引継ぎをしないまま退職することで会社に大きな損害が発生する可能性があります。
何らかの事情で後任者へ直接引継ぎするのが難しい場合でも、最低限、引継ぎ書を残すようにしましょう。余裕があれば、取引先や顧客などの関係者に退職の挨拶を済ませておくのもおすすめです。
会社との交渉権がある退職代行を利用する
一口に「退職代行サービス」とは言っても、運営主体によって代行できる業務範囲は大きく変わります。民間の退職代行サービスの場合、退職の意思表示や退職手続きの代行をすることができます。しかし、民間の退職代行サービスは、弁護士とは異なり、会社に対して交渉や請求などの対応はできません。
もしも退職に併せて未払い賃金の請求なども行いたい場合や、会社から損害賠償を求められる可能性があると感じたら、弁護士が提供する退職代行サービスを利用しましょう。
しかし、弁護士の退職代行サービスは一般的に民間よりも高額です。本当に必要があるかを考えてから依頼しましょう。訴訟リスクがない場合は、リーズナブルな民間の退職代行でも十分かもしれません。オーバースペックにならないよう、まずは民間の退職代行の無料相談サービスを利用してみるのもおすすめです。
11.ポイントさえ抑えれば損害賠償リスクは低いのでご安心を
退職代行を利用して退職する際、損害賠償を請求されるリスクは基本的に低いです。しかし、無断欠勤や業務の引継ぎを怠った場合など、会社に実際の損害を与えたと認められると請求される可能性があります。
特にブラック企業では脅迫的な請求をされることもあるため、法的に対応できる弁護士監修の退職代行を選ぶと安心です。損害賠償のリスクを回避し、スムーズに退職したい方は、信頼できる退職代行を検討してみましょう。