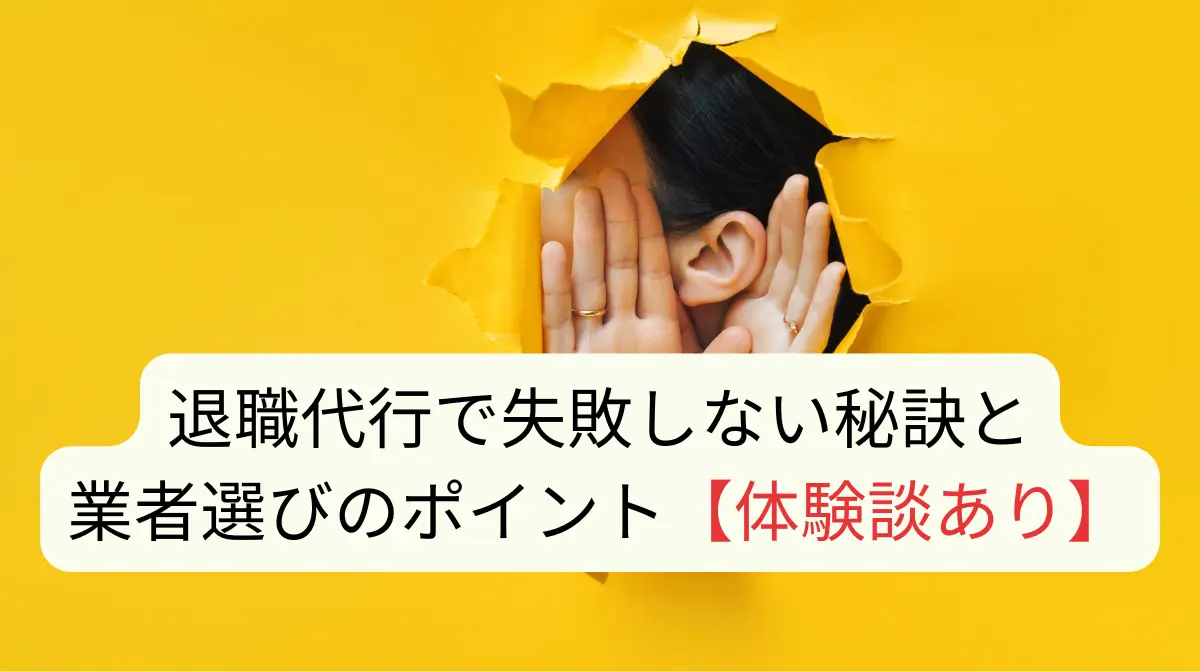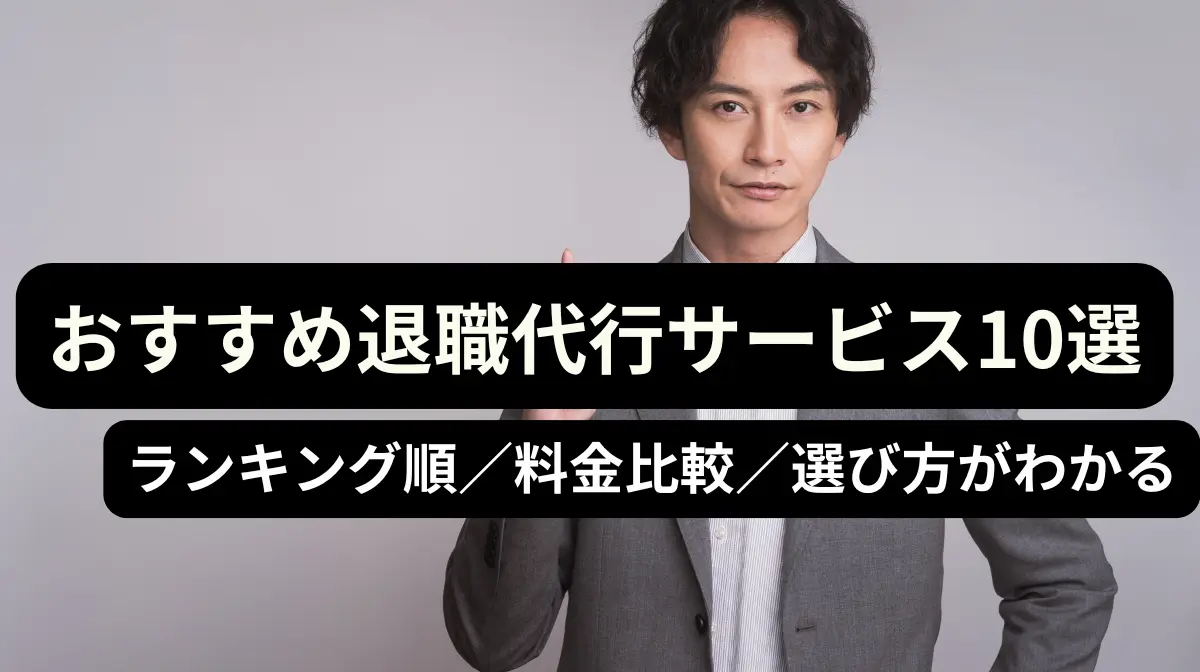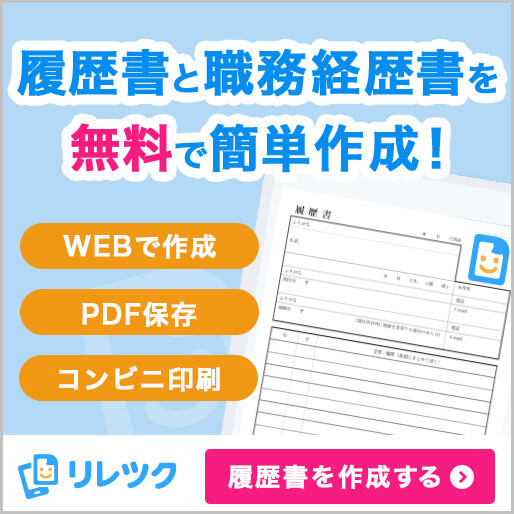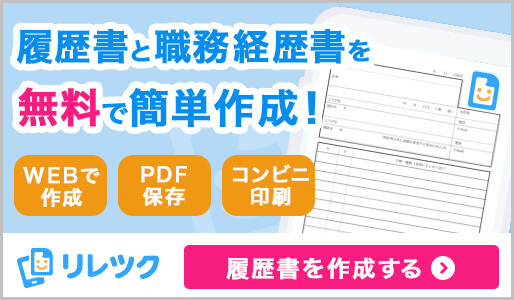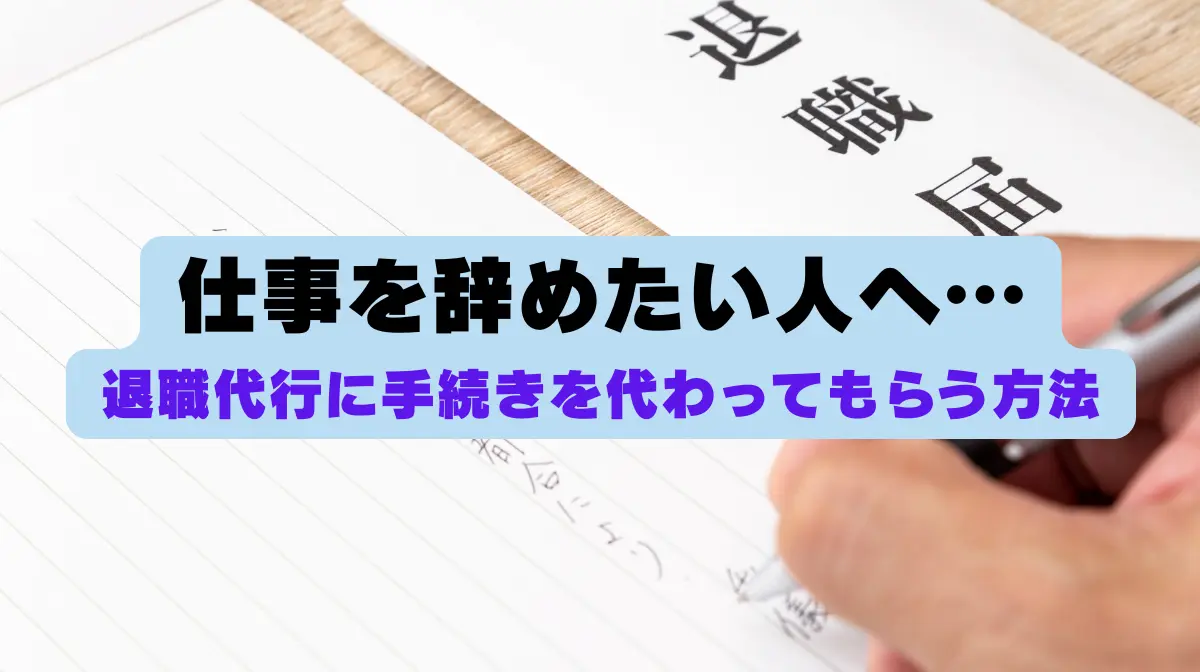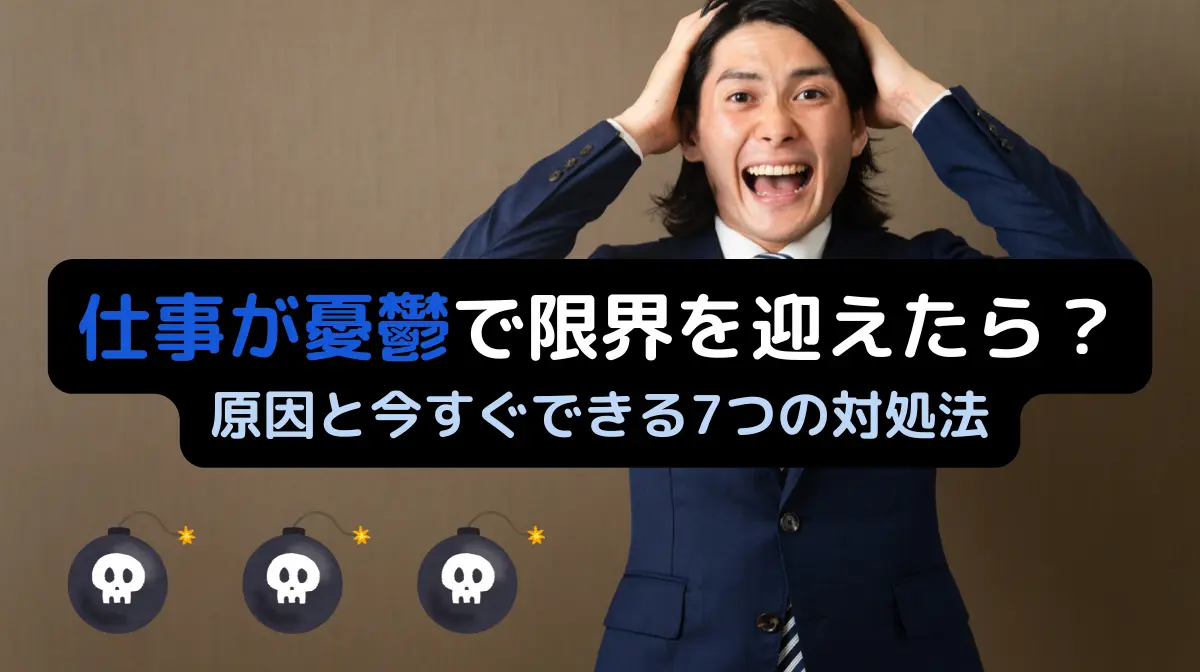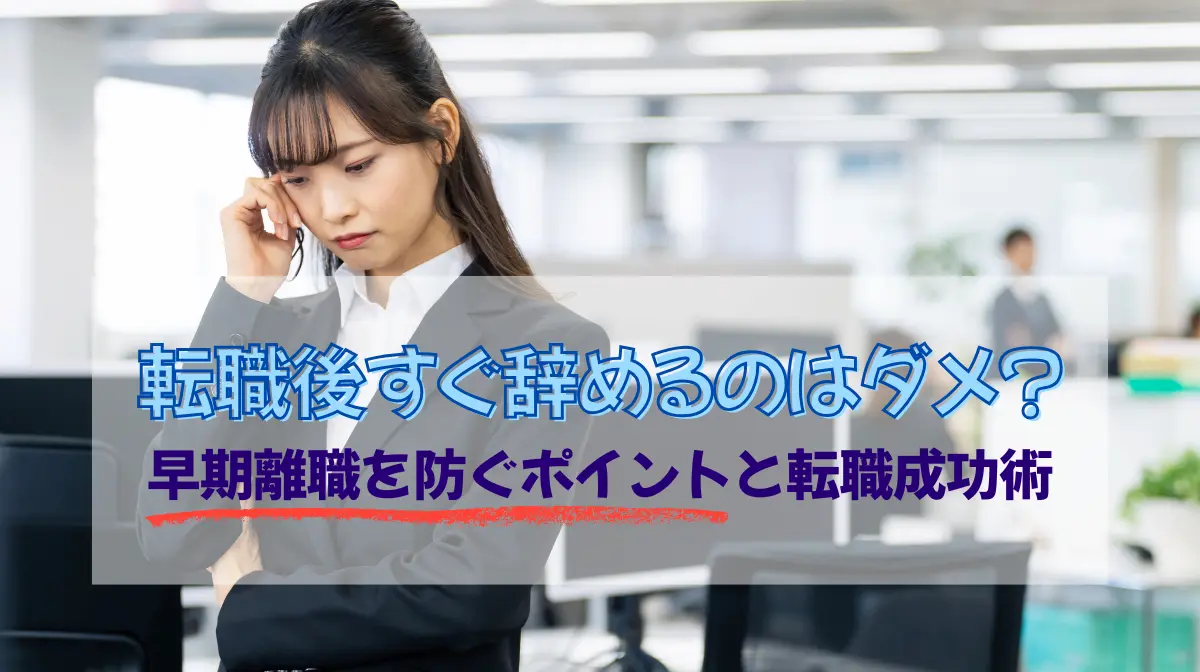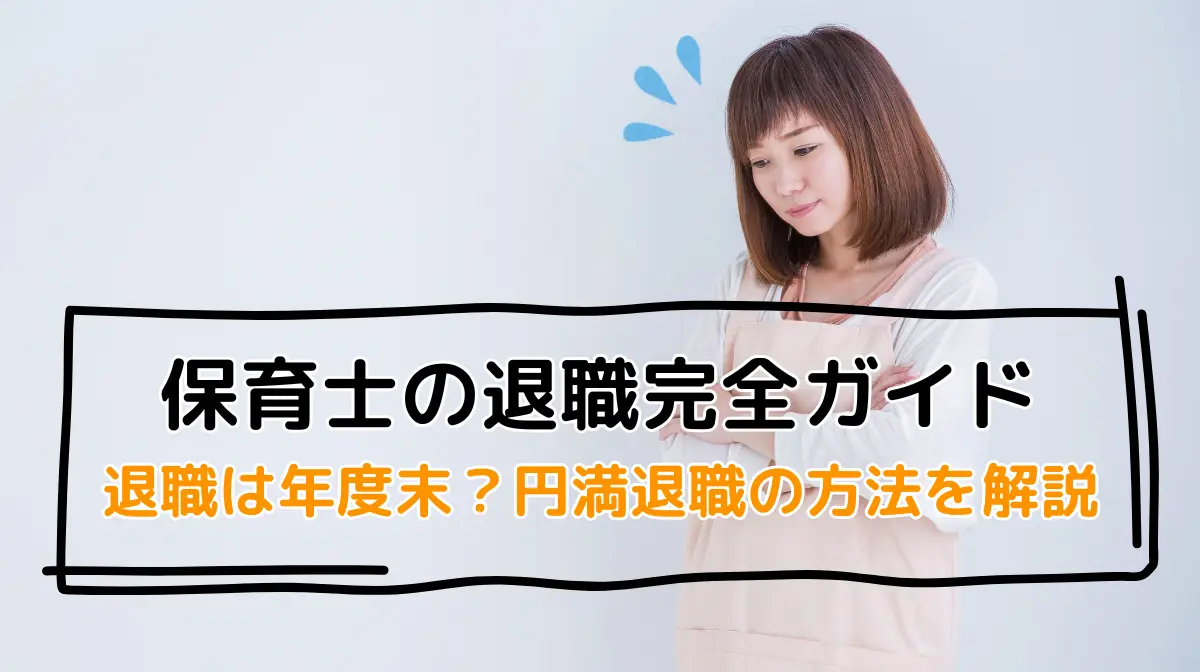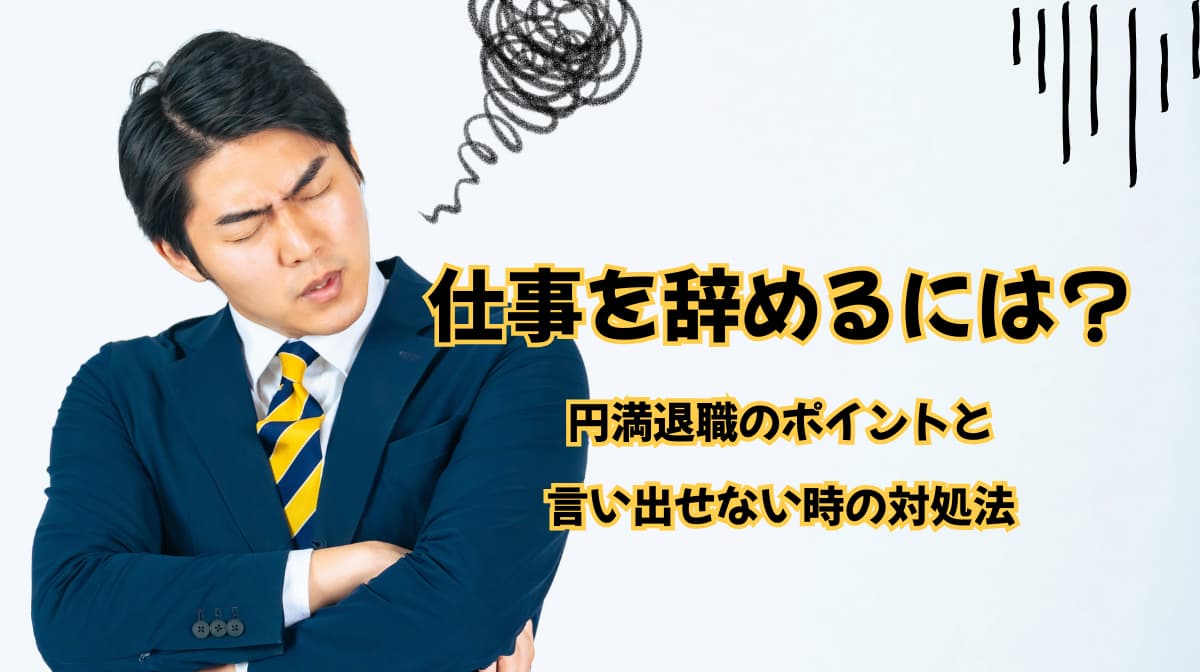近年、自分で会社に退職を言い出せない方のために「退職代行」サービスが注目を集めています。しかし、退職代行サービスが普及するにつれて「退職代行を利用して失敗してしまった…」という声も増えつつあるのが現状です。
「退職代行が失敗して、損害賠償を求められた」
「安い業者を選んだら結局自分で会社に連絡することになった」
「退職後1ヶ月経っても離職票が届かない」
そんなトラブルに見舞われた例もあるようです。そこで、本記事では退職代行が失敗する5つのパターンと対策についてまとめました。【失敗しないためのオリジナルチェックリスト】も必見です。
- 退職代行が失敗する5つの典型的なパターンと対処法
- 信頼できる退職代行業者を選ぶための5つの具体的な秘訣
- 実体験に基づく成功事例・失敗事例と、おすすめの退職代行サービス3選
1.退職代行が失敗する5つのパターン

まずは退職代行の失敗にどのようなパターンがあるのか、見ていきましょう。
お金を払ったのに退職ができなかった
実際のところ、退職代行に依頼した場合に「退職できなかった」というトラブル報告はほとんど見られません。会社側も退職代行会社からの連絡を受けると、ほとんどの場合は退職に応じているようです。
民法627条1項により、無期雇用の労働者には退職の自由が認められています。つまり、会社が「辞めさせない」と言っても法的には無意味です。
参考:民法627条1項
したがって、退職自体ができない心配はあまりない代わりに「退職できたけど余計な費用がかかった…」「会社から訴えられた…」というように、退職はできたけど幸せではない状態に陥ることに注意しましょう。以下で詳しく述べていきます。
会社から損害賠償を請求された
会社を突然辞めることで、会社から損害賠償請求をされるケースを心配している方も多いでしょう。
結論から言えば、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償が認められることは考えにくいです。従業員1名が退職したことで、直ちに会社に損害が生じることは通常は想定されません。
ただし、これも絶対ではありません。過去には、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります(ケイズインターナショナル事件:平成4年9月30日東京地方裁判所判決)。
参考:全国労働基準関係団体連合会「ケイズインターナショナル事件」
労働問題.comケイズインターナショナル事件
極端なケースを除けば、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要です。専門の業者に依頼すれば、適正な手段で退職までの道筋をつけてくれるため、このようなリスクはさらに低減できます。
懲戒解雇扱いにされた
退職代行を利用したことで懲戒解雇扱いにされるリスクも心配されるかもしれませんが、結論から申し上げますと、退職代行を利用したことを理由とする懲戒解雇に法的効力はありません。
懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う解雇のことで、日本の労使間で許容されるペナルティのうち最も重い処分です。日本では労働者の立場は手厚く保護されており、懲戒解雇は例えば会社の金を横領したなどの実害が生じるほどの『重大な問題』が認められなければ法的有効性は認められません。
退職代行を利用すること自体は、労働者の正当な権利行使であり、懲戒解雇の理由にはなりません。もし無断欠勤などがあった場合でも、それだけで直ちに懲戒解雇が認められるわけではありません。このリスクについても、過度に心配する必要はないでしょう。
退職意思を伝えた後にパワハラやいじめ・嫌がらせにあった
退職の意思を伝えた後、実際に退職するまでの間にパワハラやいじめ、嫌がらせに遭うリスクは確かに存在します。例えば、以下のような事例があります。
6年間勤めた不動産関係の会社を、ステップアップのために退職しようと、半年前、退職の意向を社長に伝えましたが、良いように丸め込まれてしまって、退職を受け入れてくれませんでした。
退職の意志が固かったため後日、退職代行を通して再び退職させてほしいと社長に伝えたところ、社長の態度が急変し、男性を激しく罵倒する言葉がSNSに届くようになったそうです。
退職の通知を送った場合に退職の効力が生じるのは2週間後です。その間のパワハラやいじめを避けるためには、有休を活用するのが効果的です。
消化できる有給がない場合は、退職までの出勤について会社と相談しましょう。例えば、有給休暇ではなく通常の欠勤として会社に2週間行かないという選択肢もあります。退職代行サービスを利用する際は、このような対応も含めて相談することが大切です。
退職代行に依頼すると、退職手続きの代行を一任できますが今回のケースのようにSNSに悪口を書かれる、プライベートの携帯電話に執拗に引き止めの電話がかかってくる、といったことは避けにくいので注意が必要です。
退職後の必要書類が届かなかった
退職した場合には、会社から離職票などの書類を送ってもらったり私物の返還を受けたりしなければなりません。特に離職票は雇用保険の申請に必要な重要な書類です。
『退職代行を依頼し、退職できた』という点では成功かもしれませんが、会社からこういった書類を送ってもらえなかったり私物も返してもらえなかったりするケースがあると、素直に成功と喜ぶには抵抗があるでしょう。
2月末で精神的な病気を理由に退職しました。3月に入ってもなかなか離職票などの必要な書類を送ってもらえず、何度も催促し、今日やっと雇用保険被保険者離職証明書が送られてきたのですが…もし失業手当を貰う手続きをするとしたら、この書類と印鑑などの必要なものをハローワークに持参し手続きをすればいいのでしょうか?退職日から一ヶ月も経ってしまっているので、失業手当を貰うことはできないのでしょうか?
このようなリスクは、退職の代行を頼む・頼まないとは別に生じ得ます。この場合は、ハローワーク等に速やかに相談しましょう。書類を渡すことを故意に遅らせる行為はあなたの退職に対する嫌がらせかもしれません。
離職票の発行については、ハローワークに相談するとハローワーク側から会社へと発行をするように要請を行ってもらうことができます。
2.退職代行選びで失敗しないための5つの秘訣
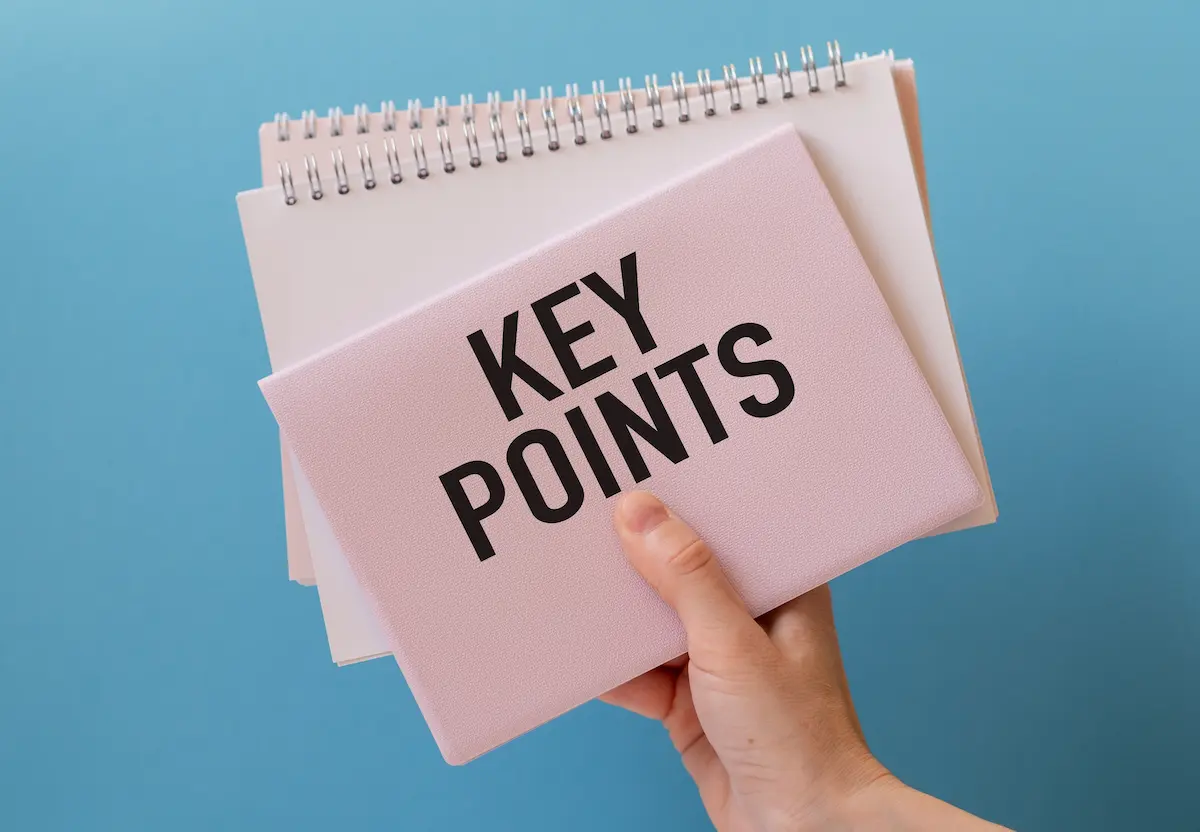
退職代行サービスを選ぶ際に失敗しないためには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。以下の5つの秘訣を押さえておきましょう。
秘訣1:退職成功率の高い退職代行サービスを選ぶ
退職代行サービスを選ぶ際、「退職成功率」を確認しましょう。信頼できる業者は自社のサイトに具体的な数字(例:「退職成功率100%」「〇〇件の退職実績」など)を掲載しています。
また、返金保証や後払いに対応している業者もおすすめです。失敗しない自信があるからこそ、全額返金や完全後払いなど消費者にとって有利なやり方を定めても運営が可能だと言えるでしょう。
秘訣2:サービス内容と対応範囲を事前に明確に確認する
退職代行サービスごとに対応できる範囲は異なります。事前にサービス内容と対応範囲を明確に確認しておきましょう。
一般企業が運営する退職代行サービスでは、基本的に退職の意思表示や手続きの代行といった基本的なことが依頼できますが、それ以上の交渉(有給消化や退職金請求など)はできないため、注意が必要です。
また、過剰なサービスは料金アップの原因となることもあります。自分が本当に必要とするサービス範囲を見極め、それに合ったサービスを選ぶことが大切です。例えば、単に退職の意思を伝えるだけでよい場合は、弁護士の退職代行サービスを選ぶと割高です。
秘訣3:料金体系の透明性と追加費用の有無をチェック
退職代行サービスの料金体系は様々です。基本料金だけでなく、追加料金の有無もしっかり確認しておきましょう。
退職代行サービスの主な料金体系
| サービスタイプ | 一般的な料金帯 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般企業型 | 2〜3万円程度 | 退職意思の伝達のみ、交渉はできない |
| 労働組合型 | 2〜4万円程度 | 団体交渉権あり、有給消化などの交渉可能 |
| 弁護士型 | 3〜8万円程度 | 法的交渉可能、トラブル時の対応も可能 |
注意すべきは「隠れた追加費用」です。例えば以下のような追加費用が発生する可能性があります。
- 退職金や残業代請求の成功報酬(回収額の20%など)
- 特急料金(即日対応の場合など)
- 書類郵送料
- 特殊なケース(役員、個人事業主など)の追加料金
料金が安すぎるサービスには注意が必要です。相場よりも大幅に安い場合、サービス内容が限定的だったり、実際には追加料金がかかったりする可能性があります。料金に見合ったサービス内容かを判断する基準として、上記の表を参考にしてください。
秘訣4:ユーザーレビューを徹底的に調査する
退職代行サービスを選ぶ際は、実際の利用者のレビューをチェックすることが重要です。
信頼できるレビューの見分け方
- 単なる「良かった」という評価ではなく、具体的なエピソードが書かれているもの
- 利用した時期や職種などの情報が含まれているもの
- ポジティブな面だけでなく、課題点や改善点も記載されているもの
注意点として、サービス提供元のサイトに掲載されているレビューだけでなく、第三者のサイトや口コミサイトの情報も確認することをお勧めします。
実績の確認方法
- 会社の設立年や運営期間
- 対応実績件数(具体的な数字があるか)
- メディア掲載実績
- 運営会社の透明性(運営元の情報が明確に記載されているか)
口コミ情報を活用する際は、極端な評価(非常に良い評価や非常に悪い評価)だけでなく、平均的な評価にも注目してバランスの取れた判断をすることが大切です。
秘訣5:退職後のフォロー体制を確認する
退職代行サービスを利用した後も、様々な手続きや対応が必要になることがあります。退職後のフォロー体制もしっかりチェックしておきましょう。
退職後に必要なサポート内容
- 離職票などの必要書類の取得サポート
- 会社からの問い合わせ対応
- 給与や退職金の精算確認
- 失業保険の申請サポート
- 転職活動のサポート
フォロー期間のチェックポイント
多くの退職代行サービスは、フォロー期間を設定しています(1ヶ月、3ヶ月など)。しかし、会社からの書類送付が遅れたり、トラブルが長引いたりすることもあります。長期間のフォローがあるサービスを選ぶと安心です。
3.退職代行による失敗を回避するための「チェックリスト」
📋 業者選定前の基本チェック
✅ 運営体制の確認
- [ ] 運営会社が明確に記載されている
- 会社名、代表者名、所在地がHP上に明記されている
- 設立年月日が記載されている(設立3年以上が望ましい)
- [ ] 運営形態を確認済み
- [ ] 一般企業型(退職意思の伝達のみ)
- [ ] 労働組合型(交渉権あり)
- [ ] 弁護士型(法的対応可能)
- [ ] 許可・資格を確認済み
- 弁護士なら弁護士登録番号
- 労働組合なら組合番号
- 一般企業なら法人登録情報
✅ 料金体系の透明性
📋 サービス内容の詳細チェック
- [ ] 基本料金が明確
- 追加料金の発生条件が明記されている
- 相場から大きく外れていない(1万円以下や10万円以上は要注意)
- [ ] 隠れコストがない
- 成功報酬の有無と率を確認
- 書類作成費、郵送費等の別途費用を確認
- キャンセル料の規定を確認
✅ 対応範囲の確認
- [ ] 基本対応を確認
- 退職意思の伝達
- 退職日の調整
- 必要書類の依頼
- [ ] 交渉対応の可否
- [ ] 有給消化の交渉(労働組合・弁護士のみ可能)
- [ ] 残業代請求の交渉(弁護士のみ可能)
- [ ] 退職金の交渉(弁護士のみ可能)
- [ ] 緊急対応
- 即日対応の可否
- 深夜・早朝対応の可否
- 土日祝日対応の可否
✅ アフターサポートの充実度
- [ ] フォロー期間を確認
- フォロー期間(1ヶ月、3ヶ月、無期限など)
- フォロー期間中の対応範囲
- [ ] 必要書類取得サポート
- 離職票取得のサポート
- 源泉徴収票取得のサポート
- 年金手帳等返却物の受け取りサポート
📋 信頼性・実績の確認
✅ 実績・評判の調査
- 具体的な実績数値
- 退職成功率(100%近いか)
- 累計対応件数(数百件以上が望ましい)
- 運営年数(3年以上が望ましい)
- 第三者評価の確認
- Google口コミの評価(4.0以上)
- SNSでの評判
- 消費者センターへの苦情の有無
- メディア掲載実績
- テレビ、新聞、雑誌での紹介実績
- 専門家からの推薦コメント
✅ 保証制度の有無
- 全額返金保証
- 退職できなかった場合の返金保証
- 返金条件が明確に記載されている
- 損害補償
- 万が一のトラブル時の補償制度
- 責任保険への加入状況
📋 契約前の最終確認
✅ 契約内容の詳細確認
- 契約書面の内容
- 契約条件が書面で明確に記載されている
- クーリングオフの適用可否
- 個人情報の取り扱い方針
- 担当者との相性
- 相談時の対応が丁寧
- 質問に対して明確に回答
- 不安な点をしっかり解消してくれる
✅ 危険な業者の特徴(要注意)
- 以下の特徴がないか確認
- ❌ 会社情報が曖昧・非公開
- ❌ 極端に安い料金(1万円以下)
- ❌ 「100%成功」など過度な宣伝
- ❌ 契約を急かす営業手法
- ❌ 口コミが極端に少ない、または怪しい
- ❌ 法的資格なしに交渉を約束
📋 退職決行前の準備チェック
✅ 個人準備
- 必要な情報を整理
- 勤務先の正式名称・所在地・連絡先
- 直属上司・人事担当者の氏名
- 雇用契約書・就業規則の内容確認
- 退職後の手続き準備
- 健康保険の切り替え準備
- 年金手続きの準備
- 失業保険申請の準備
✅ 最終確認事項
- 退職理由の整理
- 今後の転職活動で説明できる理由を準備
- 同僚・友人への説明内容を整理
- 緊急連絡先の確保
- 退職代行業者の緊急連絡先
- トラブル時の相談先(労働基準監督署等)
🚨 即座に契約を避けるべき危険サイン
絶対に避けるべき業者の特徴
- 会社概要が不明確:所在地や代表者名が記載されていない
- 格安すぎる料金:相場の半額以下(5,000円〜10,000円)
- 法的根拠のない約束:一般企業なのに「交渉します」と断言
- 口コミが不自然:同じような文章の高評価レビューばかり
- 契約を急かす:「今日中に決めないと料金が上がる」等の圧迫
- 連絡手段が限定的:メールのみ、LINEのみなど
トラブル回避の鉄則
- 複数業者を比較検討する(最低3社以上)
- 不明な点は契約前に必ず質問する
- 口約束ではなく書面での確認を求める
- 家族や信頼できる人に相談してから決める
このチェックリストで1つでも不安な項目があれば、その業者は避けることをお勧めします。
4.退職代行サービス利用者の体験談

実際に退職代行サービスを利用した方々の体験談から、成功と失敗のポイントを学びましょう。
成功事例:スムーズに退職できたケース
Aさん(30代・男性・IT業界)の場合
パワハラ気質の上司が退職を受け入れてくれず、何度申し出ても「人手不足だから」と先延ばしにされていました。心身ともに限界を感じ、弁護士運営の退職代行サービスに依頼しました。
弁護士から会社に連絡が入った翌日から出社不要となり、有給休暇も全て消化できました。想像以上にスムーズで、「もっと早く利用すればよかった」と思いました。
失敗事例:トラブルに発展したケース
Bさん(20代・女性・小売業)の場合
料金の安さだけで選んだ退職代行サービスに依頼しました。確かに退職の意思は伝えてもらえましたが、その後の離職票が1ヶ月経っても届かず、問い合わせたところ「フォロー期間が過ぎている」と言われ、自分で会社に連絡を取らなければいけなくなりがっかりしました…。
体験者が語る「知っておくべきだったこと」
Cさん(40代・男性・製造業)の場合
退職代行を利用した後、前職の同僚から「なぜ突然辞めたのか」と連絡がきて困りました。退職の理由をどう説明するか、周囲にどう伝えるかまで考えておくべきでした。また、退職金の計算方法が複雑で、予想より少ない金額になってしまいました。事前に退職金の計算方法を確認しておけば良かったと思います。
経験談から考える失敗と成功のポイント
退職代行を利用したことでスムーズに退職できたという喜びの声がある一方で、書類の不着や周囲との人間関係の問題など予期せぬトラブルに見舞われたという報告もありました。
これらの実体験を元に考えると、退職代行を利用すれば退職自体は簡単にできますが、自分のなかで退職についてなんの準備もしていないまま依頼をすると、失敗につながりやすいと言えます。
退職したいと思ったとき、退職代行を利用すれば手続きの一切を任せることができますが、なにも考えず丸投げするのは危険です。
①信頼できる退職代行業者を選ぶ
②退職について心の準備をしておく
③手続き等に不備がないか自分でも確認する
など、完全に他人任せにするのではなく要所要所できちんと準備・判断・確認することが望ましいでしょう。
5.おすすめの退職代行サービス3選
信頼性、サービス内容、料金などを総合的に考慮し、おすすめの退職代行サービスを3つご紹介します。
退職代行セカステ

特徴
- 株式会社が運営
- 元労務担当者が対応
- 行政書士監修
- 退職できなかった場合は全額返金保証
サービス内容
- 勤務先への連絡不要
- 365日24時間、全国からの相談に対応
- 退職後の社会保険給付金と失業保険関連の相談可能
- 行政書士法人と連携して退職届の作成も代行可能
料金
- シンプルな料金体系(21,800円 追加料金なし)
- 相談は無料
- 退職できなかった場合には全額返金保証付き
セカステは特に、使いやすさと充実したアフターサポートに強みがあります。利用者のレビューも高評価で、「何度も辞めようと思ったが言い出せなかったのが、その日のうちに退職が完了した」「不明なことが多かったが担当者が真摯に対応してくれた」といった声が寄せられています。
リーガルジャパン

特徴
- 労働組合が運営
- 弁護士監修
- 全額返金保証あり
サービス内容
- 即日退職サポート
- 有給消化サポート
- 退職後のサポート
- LINEでの相談は24時間対応
- 必要な手続きはすべて郵送でOK
料金
- 正社員/パート職種問わず25,000円(別途、労働組合加入費2,000円が必要)
- サポート内容:無制限のチャット相談、有給消化サポート、必要書類の受け取りサポート、退職届の作成サポート、転職サポート
リーガルジャパンは労働組合が運営しているため、退職の意思を伝えるだけでなく、有休消化などの会社との交渉にも対応できる点が強みです。また、離職票などの必要書類の受け取りサポートや転職支援も行っており、退職後のフォローも充実しています。
弁護士法人みやび
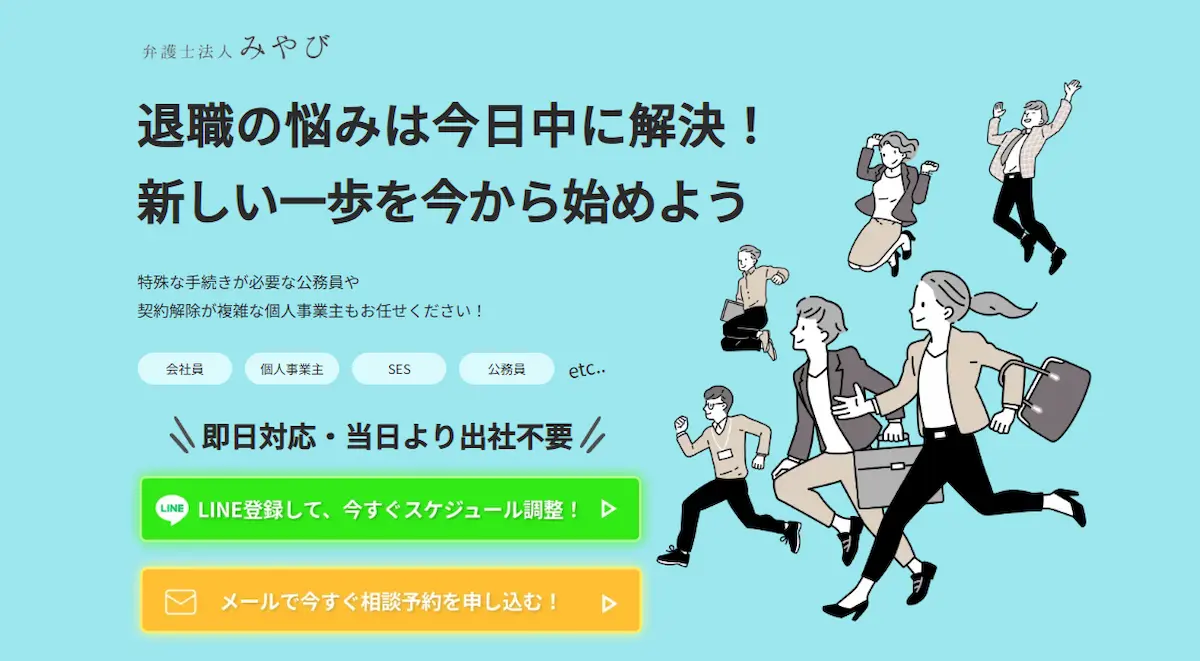
特徴
- 弁護士事務所が運営
- 弁護士が直接対応
- 無期限サポート
サービス内容
- すべて弁護士に丸投げ可能
- 弁護士が責任を持って会社介入
- 各種金銭請求交渉(有給消化・残業代・退職金・未払い給与の請求)
- パワハラ・セクハラ時の損害賠償請求も交渉可能
- 無料相談(LINE・Email)で全国24時間対応
料金
- 料金は三体系27,500円/55,000円/77,000円(職業や依頼内容による)
- オプション費用:回収額の20%(残業代・退職金請求など)
みやびは弁護士が直接対応し、退職後も無期限でサポートを行う点が大きな特徴です。特に複雑なケース(残業代請求、損害賠償対応など)や、万が一のトラブルに備えたい方にお勧めのサービスです。弁護士ならではの法的交渉力を活かした解決実績も豊富です。
もっとおすすめの退職代行サービスについて知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。
6.退職代行に関するよくある質問と回答

退職代行サービスに関するよくある質問とその回答をまとめました。
退職代行サービスは法的に問題ないのか
退職代行の法的位置づけ
退職は労働者の権利であり、退職の意思を第三者が代わりに伝えること自体に法律上の問題はありません。ただし、退職代行業者が行える行為には制限があります。
弁護士法との関係
一般の退職代行業者(弁護士・労働組合以外)が会社と「交渉」を行うことは、弁護士法が禁止する「非弁行為」に該当する可能性があります。退職の意思を伝えるだけであれば問題ありませんが、退職条件や金銭的な交渉は原則としてできません。
利用者側のリスク
法的に認められた退職代行サービスを利用する分には、利用者側にリスクはほとんどありません。ただし、非弁行為を行う業者を利用すると、トラブルに発展する可能性があります。弁護士または労働組合が運営するサービスを選ぶと安心です。
退職代行を使った場合の履歴書の書き方
退職理由の記載方法
履歴書や職務経歴書に「退職代行を利用した」と記載する必要はありません。一般的な退職理由(「一身上の都合」「キャリアアップのため」など)を記載すれば問題ありません。
面接での説明のコツ
面接で退職理由を聞かれた場合も、退職代行を利用したことを伝える必要はありません。ポジティブな理由(「新しいスキルを身につけたかった」「キャリアの幅を広げたかった」など)を伝えるとよいでしょう。ただし、極端な嘘や前職の悪口は避けましょう。
転職活動への影響
適切に対応すれば、退職代行を利用したことが転職活動に悪影響を及ぼすことはほとんどありません。むしろ、ネガティブな環境から早期に脱出することで、精神的な余裕を持って転職活動に取り組めるというメリットもあります。
失業保険や退職金への影響はあるのか
失業保険受給要件への影響
退職代行サービスを利用すること自体は、失業保険の受給資格に影響しません。ただし、「自己都合退職」となるため、給付開始までに3ヶ月の待機期間が発生します(特定の理由がある場合は待機期間が短縮される場合もあります)。
退職金の取り扱い
退職代行を利用しても、就業規則に定められた退職金を受け取る権利は変わりません。ただし、自己都合退職となるため、会社都合退職に比べて退職金の金額が減額される場合があります。事前に就業規則を確認しておきましょう。
必要な手続きと注意点
- 離職票が届いたら速やかにハローワークに行き、失業保険の手続きをする
- 健康保険の切り替え手続きを忘れずに行う
- 退職金がある場合は、支給時期や金額を確認する
- 会社から必要書類が届かない場合は、ハローワークに相談する
退職代行後に会社から連絡が来た場合の対応方法
考えられる連絡内容
- 退職手続きや引継ぎに関する質問
- 会社貸与物の返却依頼
- 未払い給与や退職金の確認
- 再考の依頼
適切な対応方法
退職代行業者に連絡内容を報告し、対応方法を相談しましょう。基本的には、退職代行業者を通して対応することをお勧めします。特に、再考の依頼や引き留めには応じる必要はありません。
書類の郵送先や貸与物の返却方法など、必要最低限の事務的なやり取りのみ行い、感情的なやり取りは避けましょう。
7.退職代行を上手に使って次のステップに進もう

退職代行サービスを利用することで、精神的な負担を減らしつつスムーズに退職することが可能です。しかし、実体験を読むと残念な結果になってしまったケースも存在します。
退職代行を利用する際、失敗を避けるためには適切なサービス選びが重要です。退職代行サービスは、あなたの新しいスタートを切るための一つの手段に過ぎません。大切なのは、自分の人生を前向きに切り拓いていく意志です。あなたの新しい一歩を応援しています。
今すぐ退職したいけど、トラブルに遭いたくない…という方は、こちらの記事もご参照ください。