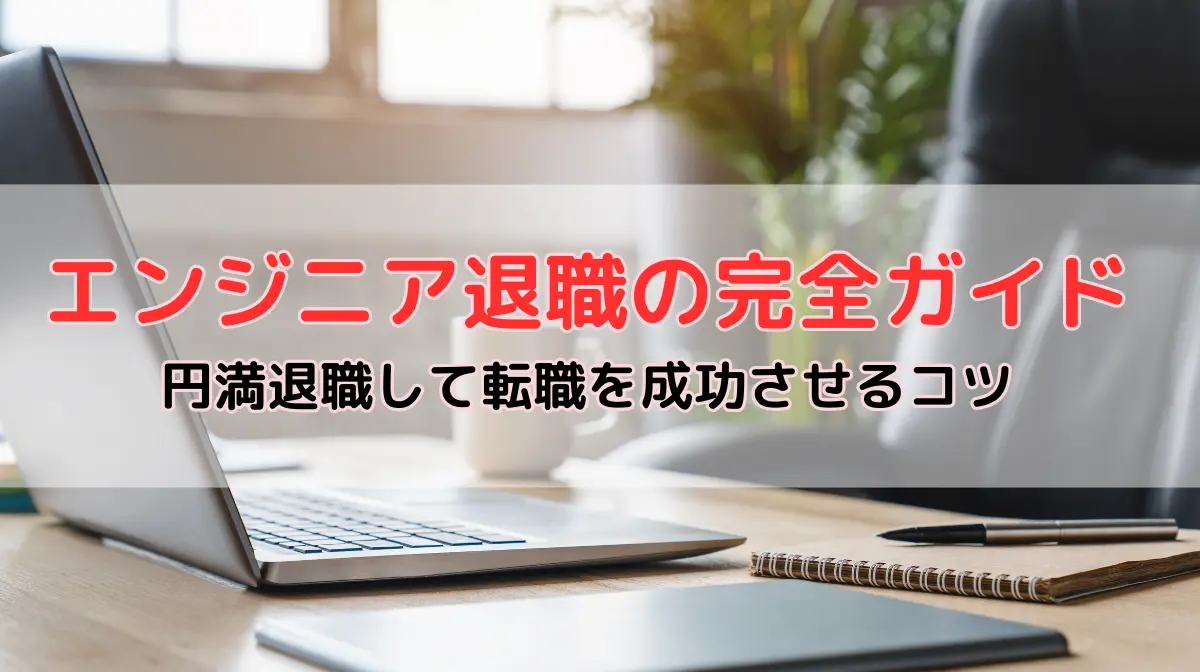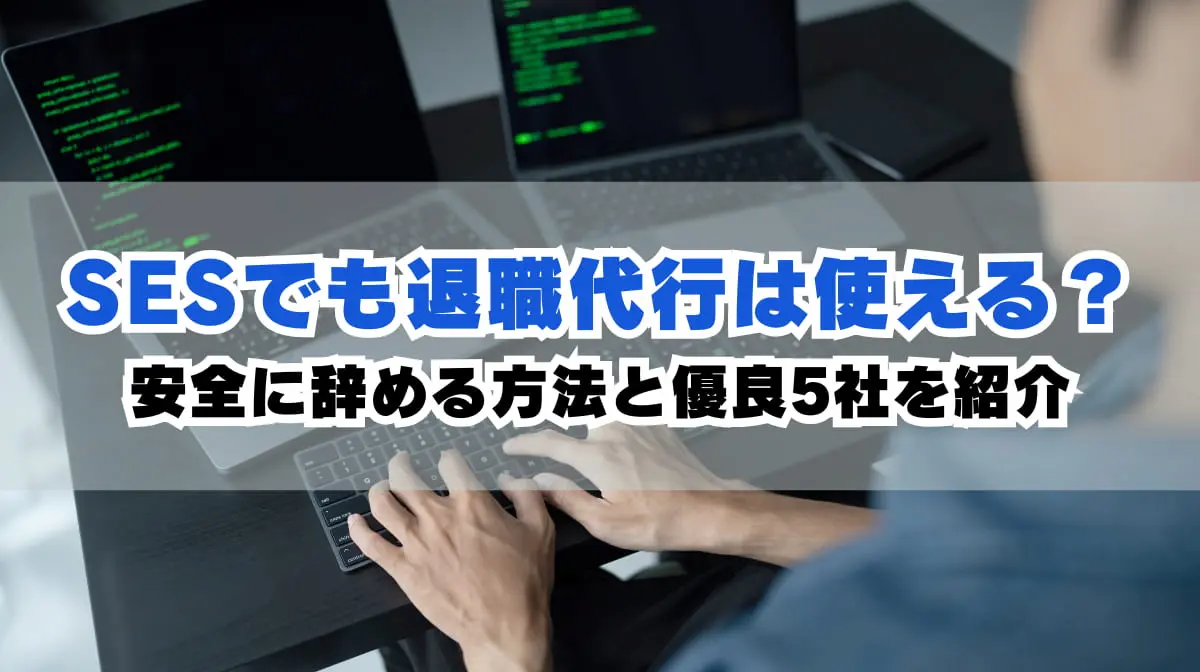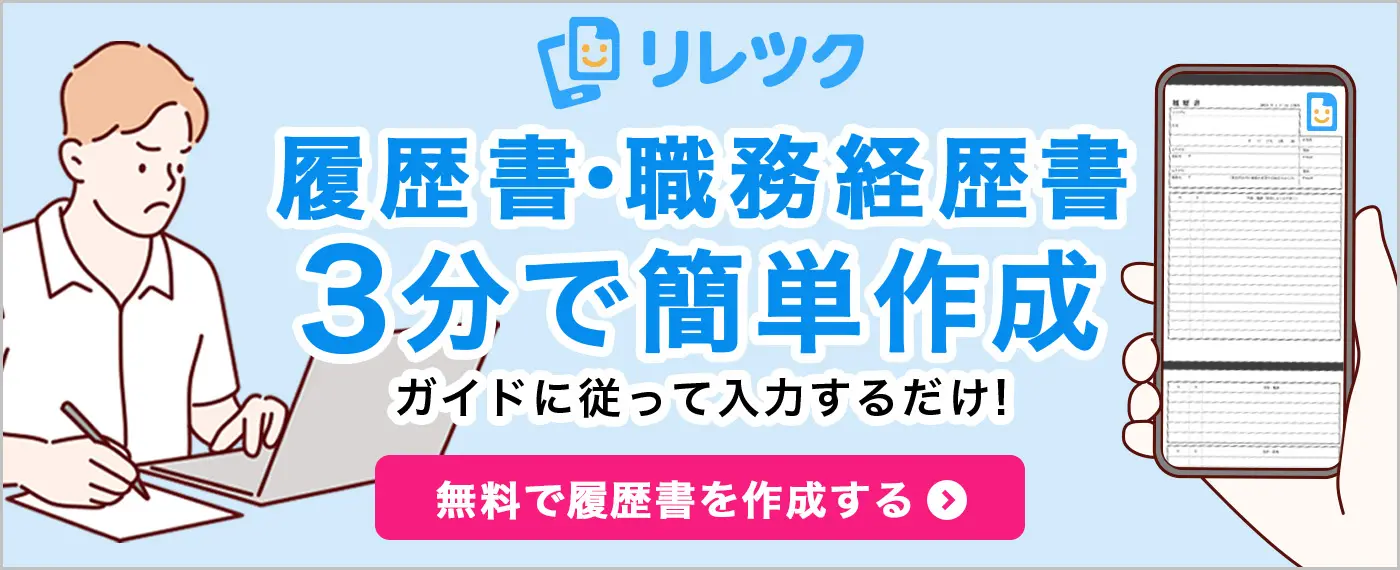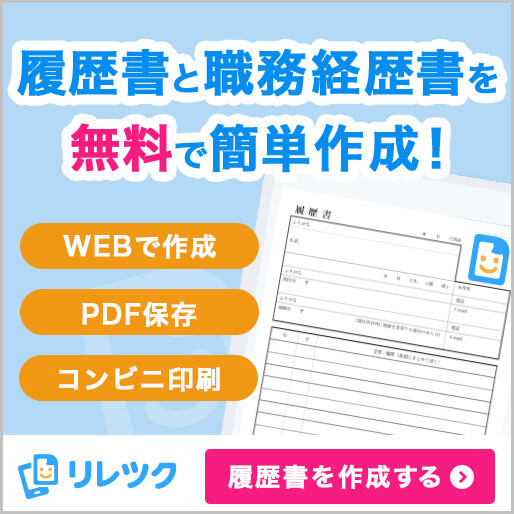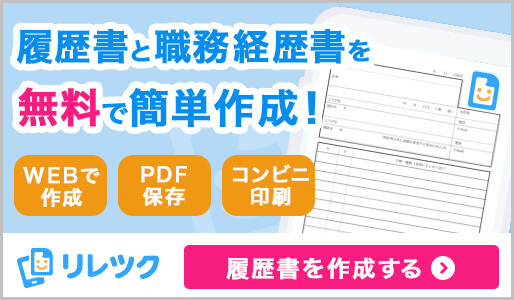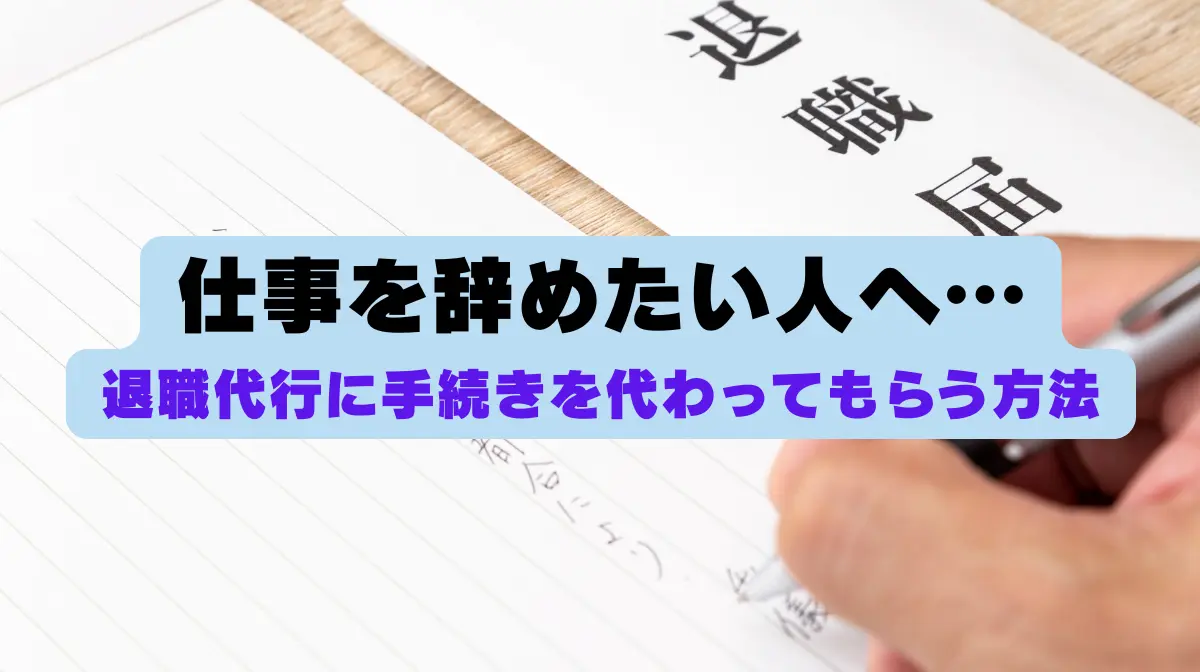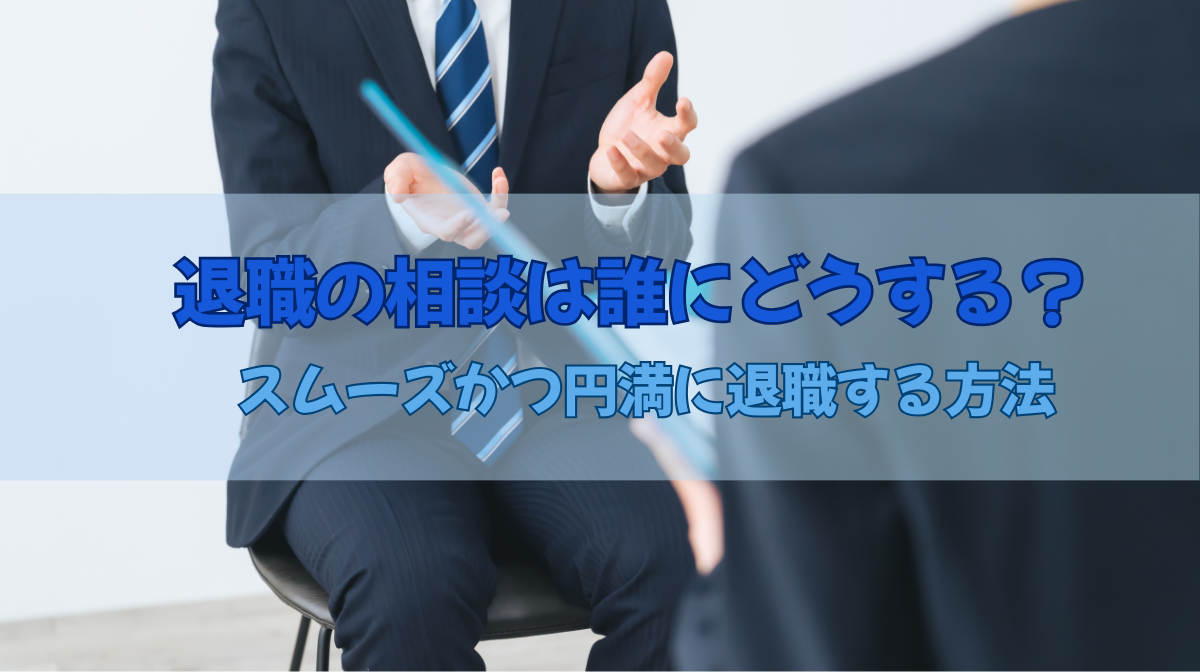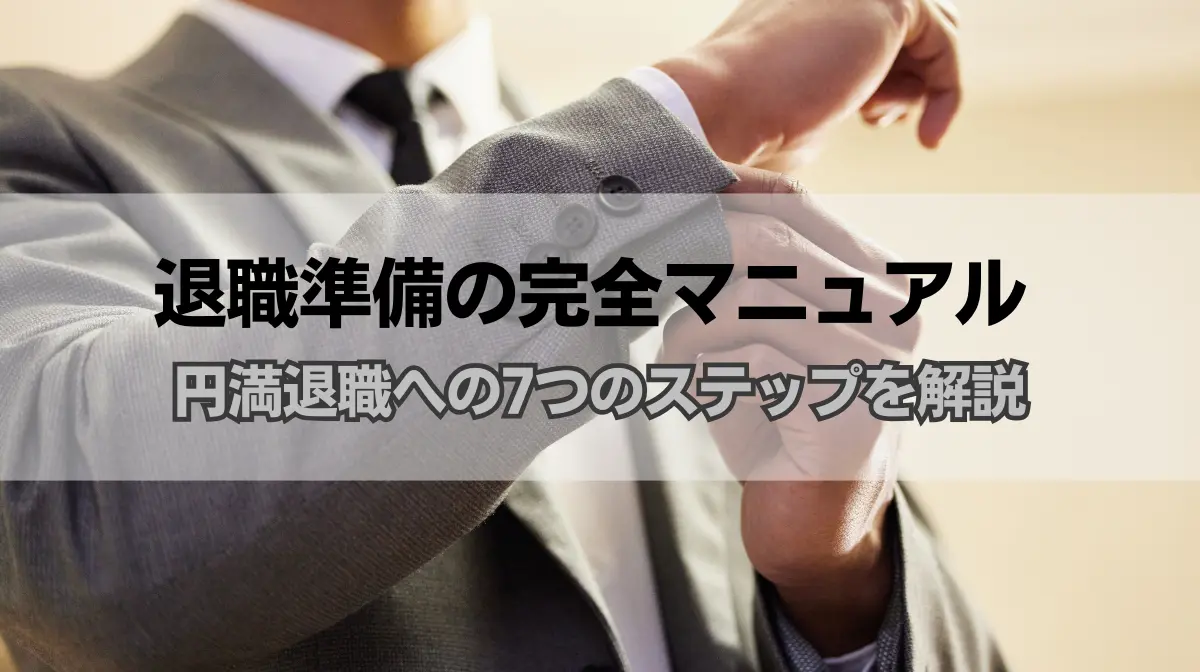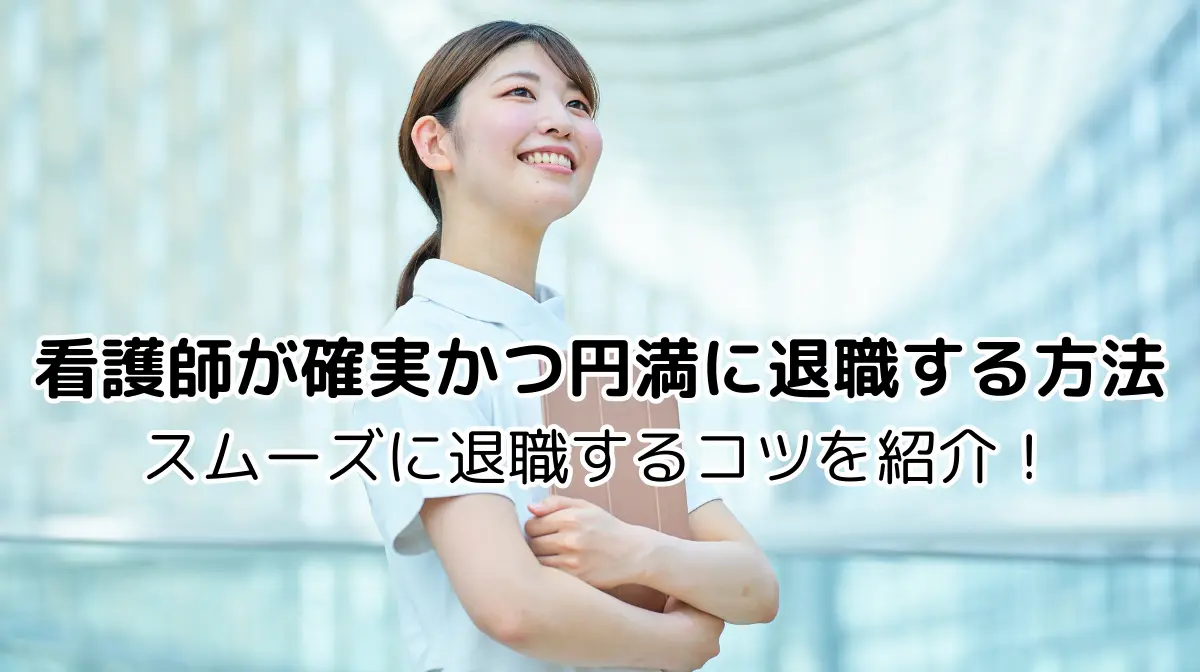エンジニアとして働く中で「会社を辞めたい」と感じている方へ。給与への不満、長時間労働、人間関係のストレスなど、退職を考える理由は様々です。
しかし「どう切り出せばいいか」「円満に辞められるか」という不安もあるでしょう。本記事では、エンジニアが円満退職を実現するための具体的な7つのステップと、避けるべきNG行動、よくあるトラブルの対処法まで詳しく解説します。
- エンジニアが退職を考える7つの主要理由と業界の実情
- 円満退職を成功させる具体的な7ステップの手順
- 退職時に避けるべきNG行動と困難な状況での対処法
1.エンジニアが退職を考える7つの理由と業界の実情

エンジニアの退職には業界特有の背景があります。実際にエンジニアが退職を決意する主要な理由を詳しく見ていきましょう。
①給与・待遇への不満があるから
エンジニアの退職理由第1位は「給与・待遇」への不満だといわれています。特に正社員エンジニアの場合、固定給制度により年収の上限が見えてしまい、スキルや成果に見合った報酬を得られないケースが多く見られます。
SES企業で働くエンジニアの場合、クライアント企業の正社員と同等の業務を担当していても、中間マージンの存在により手取り額が大幅に少なくなることがあります。また、残業代の未払いや賞与の低さも、退職を検討する大きな要因となっています。
エンジニアは市場価値が高い職種であるため、転職により年収アップを実現できる可能性が高く、給与面での不満は退職の決定的な理由となりやすいのが現状です。
②長時間労働でワークライフバランスが取れないから
IT業界では依然として長時間労働が常態化している企業が存在します。納期に追われるプロジェクトでは、深夜残業や休日出勤が当たり前となり、プライベートの時間が確保できない状況に陥ります。
特にシステム開発においては、予期せぬバグの発生やクライアントからの仕様変更により、計画通りに進まないことが頻繁にあります。その結果、エンジニアが長時間労働でカバーすることになり、心身の健康を害するリスクが高まります。
また、24時間365日の監視業務やシステム障害時の緊急対応など、エンジニア特有の業務負荷もワークライフバランスを悪化させる要因となっています。家族との時間や趣味の時間を大切にしたいエンジニアにとって、これらの労働環境は退職を考える大きな理由となります。
③キャリアアップの道筋が見えず成長が停滞するから
技術の進歩が早いIT業界において、エンジニアは常にスキルアップを求められます。しかし、会社によっては古い技術にとらわれ、新しい技術への投資や学習機会を提供しないこともあります。
同じような案件や業務の繰り返しにより、技術的な成長が感じられなくなると、エンジニアとしての市場価値の低下を懸念するようになります。特に若手エンジニアにとって、成長機会の欠如は将来への不安を増大させます。
また、マネジメントポジションへのキャリアパスが明確でない企業では、長期的なキャリア形成に不安を感じるエンジニアも多く存在します。技術者としてのスペシャリスト志向とマネジメント志向の両方に対応できるキャリアパスの整備は、エンジニアの定着において重要な要素です。
④職場の人間関係やコミュニケーションに問題があるから
エンジニアの仕事はチームワークが重要ですが、技術的な議論が感情的な対立に発展したり、上司との価値観の相違が生じたりすることがあります。特に、技術への理解が乏しい管理職との間では、仕様や工数に関する認識のズレが頻繁に発生します。
また、リモートワークの普及により、コミュニケーション不足が深刻化している職場も増えています。チャットツールでのやり取りだけでは、微妙なニュアンスが伝わりにくく、誤解や摩擦が生じやすくなります。
SES環境では、客先常駐により職場が頻繁に変わるため、人間関係の構築が困難な場合もあります。毎回新しい環境に適応する必要があり、精神的な負担が大きくなることで退職を検討するエンジニアも少なくありません。
⑤技術の変化についていけずスキルが陳腐化するから
IT技術の進歩は非常に早く、数年前に習得した技術が既に古くなっているケースは珍しくありません。新しい技術を学習する時間や機会が限られている環境では、エンジニアとしてのスキルが陳腐化する不安を抱えることになります。
会社が最新技術への投資を怠り、古いシステムの保守ばかりを任されると、市場価値の高いスキルを身に付ける機会が失われます。その結果、転職市場での競争力が低下し、将来への不安が高まります。
また、学習意欲が高いエンジニアにとって、技術的な挑戦ができない環境は非常にストレスがかかります。自己投資として私的な時間を使って学習を続けることになり、ワークライフバランスにも悪影響を与えることになります。
⑥評価制度が不透明で正当な評価を受けられないから
エンジニアの成果は数値化しにくい側面があり、適切な評価制度を設けていない企業では、頑張りが正当に評価されないことがあります。技術力の高さや問題解決能力が給与や昇進に反映されず、年功序列や人間関係が重視される職場では、優秀なエンジニアほど不満を抱きやすくなります。
特に、マネジメント経験のない管理職が技術者を評価する場合、技術的な貢献度を正確に把握できず、的外れな評価になることがあります。また、評価基準が明確でない企業では、何を頑張れば評価されるのかが分からず、モチベーションの低下につながります。
360度評価やピアレビューなど、技術者同士での評価を取り入れる企業が増えていますが、まだ十分に浸透していないのが現状です。適切な評価を受けられない環境では、エンジニアは自分の価値を正当に評価してくれる企業への転職を検討するようになります。
⑦会社の将来性に不安を感じ安定性に疑問があるから
IT業界は変化が激しく、企業の盛衰も早いため、会社の将来性に対する不安を抱えるエンジニアは多く存在します。特に、DX化の波に乗り遅れた企業や、新しい技術への投資を怠る企業では、市場での競争力低下が懸念されます。
また、経営陣の技術への理解不足により、非現実的な計画や無謀なプロジェクトが推進される企業では、エンジニアが疲弊し、会社への信頼を失うことがあります。技術的負債の蓄積や品質軽視の姿勢も、将来性への不安を増大させる要因です。
上場企業であっても、業績悪化によるリストラや事業縮小のリスクがあります。安定的なキャリアを築きたいエンジニアにとって、会社の将来性は重要な判断基準となり、不安を感じた場合は早めの転職を検討することになります。
エンジニアの方が希望する「理想の職場環境」とは
簡単にエンジニアの方が思い描く「理想の職場環境」について簡単にまとめました。このような具体的なイメージ項目を元に考えておくと、今の仕事は理想とどれぐらい乖離があるのか?もし転職するなら、どんな企業を目指せばいいのか?がより鮮明に分かるかと思います。
2.エンジニアの円満退職を成功させる7つのステップ
エンジニアの方が退職を考えるなら、できるだけ円満退職できるようにしたいと思います。そこで、エンジニアが円満退職するための工程を7つのステップとして紹介します。
エンジニアが円満退職する7つのステップ
退職タイミングを戦略的に決定する
プロジェクトの区切りが良い時期を見計らい、理想的には3ヶ月前、最低でも1〜2ヶ月前に申告。繁忙期は避けるのが賢明です。
直属上司に退職意思を正しく伝える
必ず直属の上司に最初に、「相談」ではなく「報告」として固い意志を伝えます。他の人には聞かれない会議室などの場所を選びましょう。
引き留めに負けない退職理由を作成する
「新しい技術分野に挑戦したい」など、会社の不満ではなく、前向きで個人的な成長に焦点を当てた理由を準備します。
プロジェクト引き継ぎを完璧に実行する
後任者が困らないよう、システムの仕様や設計思想、コードコメントなどを盛り込んだ丁寧な引き継ぎ資料を作成し、口頭でも説明します。
社内外に退職を適切に報告する
上司と相談の上、チームメンバーやクライアントなど関係者に適切な順序とタイミングで報告。感謝の気持ちを伝えることが大切です。
有給消化と退職手続きを完了する
引き継ぎを考慮して計画的に有給を消化します。社員証の返却や書類の受領など、手続きの漏れがないようチェックしましょう。
転職先との入社時期を最終調整する
退職日が確定したら、転職先に正式な入社日を連絡。最終出社日にはお世話になった方々へ丁寧に挨拶回りをします。
円満退職は計画的な準備と正しい手順が鍵となります。エンジニア特有の業務内容を考慮した、実践的なステップを順番に解説します。
ステップ1:退職タイミングを戦略的に決定する
円満退職の成功は、適切なタイミング選択から始まります。法的には2週間前の申告で退職可能ですが、エンジニアの場合は最低でも1〜2ヶ月前、理想的には3ヶ月前の申告が望ましいケースもあります。
できればプロジェクトの区切りを意識したタイミング設定が重要です。システムリリース直後やメジャーアップデート完了後など、自分の担当業務に一定の区切りがついた時期を選ぶことで、会社への迷惑を最小限に抑えられます。
また、会社の繁忙期(年度末、決算期、大型プロジェクト佳境)は避けるべきです。退職交渉がスムーズに進まないだけでなく、同僚からの印象も悪くなる可能性があります。転職先の入社時期との調整も含めて、戦略的にスケジュールを組み立てましょう。
ステップ2:直属上司に退職意思を正しく伝える
退職意思は必ず直属の上司に最初に伝えます。同僚や他部署の管理職に先に話すことは、上司の管理能力を疑問視されかねず、関係悪化の原因となります。
伝える際は「相談」ではなく「報告」として、退職の意思が固まっていることを明確に示します。「検討中」や「迷っている」といった曖昧な表現は、引き留めの余地を与えてしまい、交渉が長期化する原因となります。
面談の場では、感情的にならず冷静に話すことが重要です。会議室など、他の人に聞かれない場所を選び、十分な時間を確保して臨みましょう。上司も突然の話に動揺する可能性があるため、相手の気持ちに配慮した伝え方を心がけます。
ステップ3:引き留めに負けない退職理由を作成する
退職理由は、会社が改善困難で、かつ前向きな内容にすることがポイントです。「新しい技術分野への挑戦」「より専門性を深めたい」「キャリアの幅を広げたい」など、成長志向をアピールする理由が効果的です。
避けるべきは、給与、人間関係、労働環境などの不満を直接的に表現することです。これらは会社が改善提案をしてくる可能性があり、退職交渉が複雑化します。また、転職先が決まっている場合でも、企業名は明かさない方が安全です。
理由は一貫性を保ち、複数の人に話す際も内容がブレないよう注意します。事前に想定される質問への回答も準備しておくと、自信を持って対応できます。
ステップ4:プロジェクト引き継ぎを完璧に実行する
エンジニアの引き継ぎは、単なる書類の引き渡しではありません。システムの仕様、設計思想、注意点、将来の拡張性など、暗黙知も含めて後任者に伝える必要があります。
引き継ぎ資料は、技術レベルの異なる後任者でも理解できるよう、丁寧に作成します。ソースコードにはコメントを充実させ、設計書や運用マニュアルも最新の状態に更新しておきます。
口頭での説明時間も十分に確保し、実際に操作を見せながら説明することで、理解度を高めます。後任者からの質問には快く答え、退職後も一定期間は連絡可能であることを伝えると、相手も安心できます。
ステップ5:社内外に退職を適切に報告する
上司との退職交渉が完了した後、関係者への報告を行います。チームメンバー、関連部署、クライアントなど、影響範囲を整理して順序立てて進めます。
社内への報告は、上司から正式に発表されるタイミングに合わせます。個人的に親しい同僚には事前に伝えることも可能ですが、噂が広まらないよう注意が必要です。
クライアントがいる場合は、上司と相談して適切なタイミングで報告します。後任者の紹介も含めて、取引関係に支障をきたさないよう配慮します。感謝の気持ちを込めた丁寧な挨拶を心がけましょう。
ステップ6:有給消化と退職手続きを完了する
有給休暇の消化は労働者の権利ですが、引き継ぎ状況を考慮して計画的に取得します。退職日の設定時に、有給消化期間も含めたスケジュールを提示することで、トラブルを避けられます。
退職手続きには、社員証や会社支給品の返却、保険関係の手続き、退職証明書の受領などがあります。チェックリストを作成して、漏れがないよう進めます。
ステップ7:転職先との入社時期を最終調整する
退職日が確定したら、転職先に正式な入社日を連絡します。この際、余裕を持ったスケジュールを組むことで、予期せぬトラブルにも対応できます。
引き継ぎが長引く可能性も考慮し、転職先には事情を説明して理解を得ておきます。責任感のある対応は、転職先での印象も良くします。
最終出社日には、お世話になった方々への挨拶回りを行います。菓子折りを用意するなど、感謝の気持ちを形で示すことで、良い印象を残して退職できます。
3.エンジニアが避けるべき退職時の5つのNG行動

退職時の不適切な行動は、将来のキャリアに悪影響を与える可能性があります。特にエンジニアが注意すべき行動パターンを具体例とともに紹介します。
突然の退職申告で信頼関係を破綻させる
「明日で辞めます」といった突然の退職申告は、どのような理由があっても避けるべきです。エンジニアの業務は専門性が高く、引き継ぎには相応の時間が必要です。
突然の退職は、チーム全体に大きな負担をかけ、プロジェクトの進行に深刻な影響を与えます。これまで築いてきた信頼関係が一気に崩れ、業界内での評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。
緊急事態でやむを得ず急な退職が必要な場合でも、可能な限り丁寧に事情を説明し、代替案を提示するなどの配慮が必要です。
ネガティブな退職理由で会社との関係を悪化させる
「上司が嫌い」「給料が安い」「会社に将来性がない」といった批判的な退職理由を伝えることは、関係悪化の原因となります。たとえ事実であっても、建設的でない批判は避けるべきです。
ネガティブな理由は相手を不快にさせるだけでなく、改善提案という名目で引き留めが長期化する原因にもなります。また、他の社員への悪影響を懸念され、早期退職を求められる場合もあります。
前向きな理由に言い換えることで、相手も納得しやすくなり、円満な退職が実現できます。
業務引き継ぎを怠り後任者に迷惑をかける
「どうせ辞めるから」という気持ちで引き継ぎを疎かにすることは、プロフェッショナルとして最も避けるべき行為です。不完全な引き継ぎは、後任者だけでなく、チーム全体に長期的な影響を与えます。
システムの設計思想や運用ノウハウなど、文書化されていない重要な情報もあります。これらを適切に引き継がないと、将来的に大きなトラブルの原因となる可能性があります。
最後まで責任を持って業務に取り組む姿勢は、周囲からの評価を高め、良好な関係を維持することにつながります。
転職先の情報を軽率に漏らしてトラブルを招く
転職先の企業名や条件を詳しく話すことは、様々なトラブルの原因となります。競合他社への転職の場合、機密情報の漏洩を疑われる可能性があります。
また、転職先の好条件を自慢するような発言は、残る同僚の士気を下げ、人間関係を悪化させます。転職活動中であることを早い段階で漏らすことも、職場での立場を悪くする原因となります。
転職先の情報は必要最小限に留め、詳細は退職後に必要に応じて共有する程度に抑えることが賢明です。
感情的になって最後の印象を台無しにする
退職交渉中に感情的になり、これまでの不満を爆発させることは絶対に避けなければなりません。一時的な感情で、長年築いてきた関係性を台無しにしてしまう可能性があります。
引き留めや条件交渉が思うように進まない場合でも、冷静さを保つことが重要です。感情的な対応は、相手の心象を悪くし、円満退職を困難にします。
困った時は一旦時間を置いて冷静になる、信頼できる人に相談するなど、感情をコントロールする方法を用意しておくことが大切です。
4.エンジニアの転職成功につながる退職準備

退職は新しいキャリアへの重要なステップです。転職市場で有利になる退職の進め方と、長期的なキャリア戦略について解説します。
転職市場で評価される退職ストーリーの構築
転職活動において、退職理由は必ず質問される項目です。一貫性があり、説得力のある退職ストーリーを構築することが、面接での高評価につながります。
「技術的な成長」「新しい挑戦」「専門性の深化」など、ポジティブな動機を中心とした物語を作ります。具体的なエピソードを交えることで、リアリティと説得力が増します。
また、現職での経験と転職先での目標を論理的に関連付けることで、キャリアプランの一貫性を示すことができます。退職理由が転職の動機として自然に説明できるよう、しっかりと準備しておきましょう。
前職との良好な関係維持がもたらすメリット
円満退職により前職との良好な関係を維持することは、将来のキャリアにおいて大きなメリットをもたらします。エンジニア業界は意外に狭く、転職先で前職の関係者と再会することも少なくありません。
技術的な相談や情報交換、時には新しいビジネス機会の紹介を受けることもあります。また、フリーランスとして独立した際に、前職から案件を受注できる可能性もあります。
リファレンスチェックが行われる場合、前職の上司や同僚からの推薦は非常に有効です。良好な関係を維持していれば、転職活動において強力な後押しとなります。
業界内ネットワークを活用したキャリア戦略
エンジニア業界では、技術コミュニティや勉強会、カンファレンスなどを通じたネットワーキングが重要です。円満退職により築いた人脈は、これらのネットワーク拡大の基盤となります。
前職の同僚や上司との関係を維持することで、異なる企業の情報や技術トレンドを収集できます。また、転職機会の紹介を受けることもあり、隠れた優良企業との出会いの可能性もあります。
定期的な情報交換や技術的な相談を通じて、業界内での存在感を高めることができれば、キャリアアップの機会も増加します。人脈は長期的な資産として大切に育てていくことが重要です。
フリーランス転向時の円満退職ポイント
フリーランスへの転向を目指す場合、前職との関係は特に重要になります。最初の案件獲得において、前職からの依頼は非常に有効な選択肢となるからです。
円満退職により信頼関係を維持していれば、業務委託として仕事を依頼される可能性があります。適正な価格設定と品質の高い成果物の提供により、継続的な取引関係を構築できます。
また、前職の人脈を通じて新たなクライアントの紹介を受けることもあります。フリーランスとして成功するためには、人的ネットワークが重要な要素となるため、退職時の関係性は特に慎重に管理する必要があります。
5.エンジニア退職でよくある質問と解決策

退職を検討するエンジニアから寄せられる代表的な疑問に答えます。プロジェクト途中の退職やSES特有の問題など、具体的な解決策を提示します。
Q1.プロジェクト途中での退職は可能か?
A1.法的には2週間前の申告で退職可能ですが、エンジニアの場合はプロジェクトへの影響を最小限に抑える配慮が必要です。まず、プロジェクトの進捗状況と自分の担当範囲を整理し、引き継ぎ可能な状態まで進めることが重要です。
緊急性の高い退職事由がある場合は、上司に正直に事情を説明し、可能な限りの協力姿勢を示します。代替案の提示や、リモートでのサポート継続など、柔軟な対応を検討しましょう。
ただし、会社側が無理な引き留めを行う場合は、労働基準監督署への相談も検討できます。退職の自由は法的に保障された権利であることを理解しておくことが大切です。
Q2.SES・客先常駐での退職時の注意点
A2.SES契約で客先常駐している場合、自社だけでなくクライアント企業への配慮も必要になります。契約期間中の退職は、クライアントとの関係に影響を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。
まず自社の営業担当者と相談し、クライアントへの説明と後任者の手配について調整します。可能であれば、引き継ぎ期間中は後任者と一緒に業務を行い、スムーズな移行を図ります。
また、客先との直接契約や引き抜きに関しては、契約書の競業避止条項を確認し、トラブルを避けるよう注意が必要です。適切な手続きを踏むことで、円満な退職が可能になります。
Q3.上司から退職を引き延ばされたときはどうしたらいい?
A3.「もう少し待ってほしい」「プロジェクトが終わってから」といった引き延ばしは、違法な引き留めの可能性があります。まず、退職の意思が固いことを明確に伝え、具体的な退職日を設定します。書面での退職届提出により、法的な効力を持たせることも重要です。
合理的な理由なく退職を引き延ばすことは、労働者の退職の自由を侵害する行為です。労働基準監督署や労働局への相談、労働組合がある場合は組合への相談も有効な手段です。
それでも解決しない場合は、退職代行サービスの利用も検討できます。第三者が介入することで、感情的な対立を避けながら法的手続きを進めることができます。
Q4.会社にバレずに転職活動を進める方法は?
A4.転職活動中は、普段と変わらない勤務態度を維持することが重要です。面接のための有給取得が頻繁になると疑われる可能性があるため、計画的にスケジュールを組みます。
Web面接の活用により、昼休みや早朝の時間を利用した面接も可能です。ただし、職場のPCや回線は使用せず、個人のデバイスとモバイル回線を使用します。
SNSやLinkedInなどでの転職活動痕跡にも注意が必要です。プロフィールの更新や転職関連の投稿は、退職意思を表明するまで控えることが賢明です。また、同僚との会話でも転職に関する話題は避けるようにします。
6.スムーズに退職できないときには退職代行という選択肢

円満退職が困難な状況では、専門的なサポートが必要になる場合があります。
2024年10月に発表された「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」によると、個人で退職代行を利用した方の職種として1番多いのが営業(25.9%)であり、その次に多いのがクリエイター・エンジニア(18.8%)という結果でした。
参考:マイナビ 「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」
契約期間やプロジェクト期間に左右されるなかで、退職について悩むエンジニアも多いため、退職代行サービスの利用はエンジニア業界においても徐々に一般化されつつあるといえます。
この章では、退職代行サービスを利用すべきケースと適切な活用方法について説明します。
退職代行サービスを検討すべきケース
以下のようなケースでは、退職代行の利用が特におすすめです。
パワハラや嫌がらせにより精神的に追い詰められている場合
特に、上司との直接対話が困難な状況では、第三者の介入により冷静な解決が期待できます。
長期間の引き留めや違法な引き延ばしが続く場合
会社が退職届を受け取らない、有給消化を認めないなど、明らかに違法な対応をしている場合は、法的対応が必要になります。退職させたくないからと、手続きを遅らせたり、嫌がらせをするようなやり方も認められません。退職代行に依頼し、毅然とした態度で退職を進めましょう。
転職先の入社日が迫っているのに退職交渉が進まない場合
緊急性が高いケースにも退職代行は力を発揮します。ご自身のキャリアに重大な影響を与える前に、専門的なサポートを受けることが重要です。退職できないから…という理由で入社日の延長を申し出るのは、印象が悪いのでできるだけ避けたいもの。最悪のケースでは内定が覆ってしまうことも。慎重に行動しましょう。
エンジニア向け退職代行サービスの選び方
IT業界の特殊事情を理解している退職代行サービスを選ぶことが重要です。プロジェクトの途中での退職やSES契約の解除など、エンジニア特有の問題に対応できる専門性が求められます。
料金体系の透明性も重要な選択基準です。追加料金の発生条件や、失敗時の保証制度についても事前に確認しておきます。実績と口コミを調査し、信頼できるサービスを選択することが成功の鍵となります。
退職代行利用時の注意点
退職代行を利用する場合でも、可能な限り引き継ぎ資料の準備は行っておくべきです。後任者や同僚への配慮は、エンジニアとしてのプロフェッショナリズムの表れです。
また、会社支給品の返却や保険手続きなど、事務的な手続きについても事前に整理しておきます。退職代行サービスと綿密に打ち合わせを行い、スムーズな手続き進行を図ります。
退職代行利用後の転職活動では、前職との関係について面接で質問される可能性があります。事実を隠すことなく、やむを得ない事情があったことを誠実に説明できるよう準備しておくことが大切です。
7.円満退職をしてエンジニアとしての未来をもっと楽しもう

エンジニアの退職は技術者としてのキャリア発展の重要な転機です。適切な手順で円満退職を実現することで、新環境での成功確率が向上します。退職理由を明確にし、7つのステップに従って計画的に進めることが大切です。
築いた人間関係は将来の貴重な財産となります。困難な状況では退職代行サービスなどの専門サポートも検討し、自身の健康と将来を最優先に判断しましょう。